富山県下新川郡入善町椚山1511-16
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
雑話
このコーナーは、日頃感じたこと、思ったことを綴っていくコーナーです。業務には、あまり関係はありませんが、業務に対する、私の考え方、想いをこの雑話の中から汲み取っていただければ幸いです。しかも、思いついた時の不定期の掲載になりますのであしからず。

大相撲夏場所を振り返って!
2場所連続4度目の優勝を決めていた大関大の里は横綱豊昇龍の上手ひねりで敗れ、初の15戦全勝は逃した。番付編成を担う日本相撲協会審判部は八角理事長(元横綱北勝海)に昇進を諮る臨時理事会の開催を要請し、理事長は受諾。26日の横綱審議委員会(横審)への諮問も決めた。28日に名古屋場所(7月13日初日・IGアリーナ)番付編成会議及び臨時理事会で昇進が正式に承認され、「第75代横綱大の里」が誕生する。
以上がデイリースポーツの内容であるが、相撲ファンの私にとって、今場所はいろんな意味で見ごたえのある場所であったように思う。役力士の充実ぶりは久々で、内容の濃い内容であったと思う。
その中でも、大関大の里の連続優勝なるか、横綱昇進なるかということについては、全勝優勝は、逃したもののそれまでの14日間については、圧倒的な相撲で勝利をつかんだことは大の里にとっても大きな収穫であったと思う。千秋楽結びの一番。横綱豊昇龍との対戦では、上手ひねりで敗れたものの内容は勝ち相撲の内容であったと思う。両手づきからの攻めで得意の形になったものの左かいなが遊んでいたのが敗戦につながったと思う、勝負を急ぎすぎたのがその要因であったと思う。
いずれにせよ、今後大横綱になるための一つの試練であると思う。優勝インタビューの中でも、そのことにはあまり触れず、横綱推挙の話に触れていたが、私が嬉しいのは、小結の高安が優勝パレードの旗手をかって出たことだと思う。
高安は先場所、優勝決定戦で、大の里に逆転優勝をさらわれたわけであるが、高安は、大の里の師匠である二所ノ関親方の弟弟子、いろんな意味での相撲世界での結びつきを感じたりもするわけであるが、大の里は、横綱伝達式を受けた後、師匠の二所ノ関親方から雲竜型の横綱土俵入りを伝授される模様であるが、伝達式でどのような言葉を選ぶのかも楽しみである。
その他今場所を盛り上げた役力士の結果を見てみると、技能賞を受けた若隆景については、12勝3敗と結果を残し、大関昇進への足掛かりをつかんだと思う。関脇霧島についても千秋楽高安には敗戦したモノの11勝4敗と大関復帰への足掛かりをつかんだと思う。
関脇大栄翔についても、千秋楽に大関琴桜に勝利して、10勝5敗と大関昇進への望みをつないだのは、大きかったと思う。
残念なのは、大関琴桜の不調ではないかと思う。段々調子は復活しているように思うが、依然として、相撲内容がよくない。腰高であるのと、ここ一番での決め手に欠けるのが大きな要因ではないかとも思う。
最後に郷土力士の朝乃山の結果であるが、2番相撲で敗れはしたものの残りは全勝し結果は6勝1敗の勝ち越し、来場所は東幕下5枚目前後に躍進する模様。来場所の結果次第では、十両再昇進になるので期待したい。
来場所は名古屋場所。会場は、IGアリーナ(愛知国際アリーナ)で7月13日初日から開催される予定。来場所も好取組を期待したい。

棚田の魅力・日本の美しい棚田!
昨今、コメ不足が巷に溢れ、コメの値段も高止まりで推移していますが、何といってもお米は日本の主食、お米の習慣を大切にしたいと思っています。
そこで、今回は田植えの季節柄、棚田の魅力・日本の美しい棚田について話をしたいと思っています。
まず、棚田の魅力ですが、簡単にまとめると以下のようになります。
美しい景観
棚田は四季折々の風景を楽しめる場所です。春には水を張った田んぼが鏡のように空を映し、夏には青々とした稲が風に揺れ、秋には黄金色の稲穂が輝きます。冬には雪景色が広がることもあり、まるで絵画のような美しさです。
生態系の保全
棚田は多様な生き物の生息地となっています。カエルやトンボ、ホタルなどが生息し、豊かな自然環境を維持する役割を果たしています。
防災機能
棚田は雨水を蓄えることで洪水を防ぐ役割を持っています。また、土砂崩れの防止にも貢献しており、地域の安全を守る重要な存在です。
文化と歴史
棚田は長い歴史を持ち、地域の伝統や文化と深く結びついています。農作業を通じて地域の人々が協力し合い、祭りや行事が受け継がれているのも魅力のひとつです。
次に何といっても、棚田の魅力はその美しい風景にあるかと思います。以下に日本の美しい棚田として紹介されている幾つかの棚田を紹介したいと思います。
まずは、東北山形の四ヶ村の棚田を紹介したいと思います。
全国でも有数の豪雪地帯である、山形県大蔵村の四ヶ村地区。冬にはあたり一面が銀世界!大きな雪の階段のように見える景色は圧巻です。
次に紹介するのは、宮城県大張沢尻棚田です。
江戸時代から昭和中期にかけて開墾された総面積4.1ha、56枚の棚田です。
わずかな土地を切り拓いて整備された棚田で、地域の人々の手によって今も大切に管理されています。
水は天水・湧水に頼り、毎年の収穫量は、約6トン。5月中旬の田植えから、10月中旬の稲刈りまで、日本の原風景といえる稲作風景が広がります。
次は、埼玉県の江戸時代から昭和中期にかけて開墾された総面積4.1ha、56枚の棚田です。
わずかな土地を切り拓いて整備された棚田で、地域の人々の手によって今も大切に管理されています。
水は天水・湧水に頼り、毎年の収穫量は、約6トン。5月中旬の田植えから、10月中旬の稲刈りまで、日本の原風景といえる稲作風景が広がります。
最後に紹介するのは、千葉県の大山千枚田になります。
千葉県鴨川市の山のふもとにある大山千枚田は、東京から近い棚田として知られています。
「日本の棚田百選」や「つなぐ棚田遺産」にも選ばれ、375枚の棚田が階段状に並ぶ風景は圧巻!春・夏の青田から秋の稲穂、そして秋から冬にかけて例年、ライトアップされた「棚田のあかり」が開催されます。
以上4件紹介しましたが、棚田は、まだまだたくさんあります。皆さんも一度、棚田の魅力を新たにし、日本の原風景である棚田の魅力を体験しては如何でしょうか。

今年も事務所付近の桜が満開になりました!
今年も事務近くの桜が満開になりました。
毎年のことですが、自然の理に感謝したいと思っています。
今まさに日本列島南から北へ桜前線が北上していますが、ここで、私の事務所の近辺の桜の見どころ、そして、これから見頃になるであろう、東北、北海道の桜の見どころを、少し紹介してみたいと思います。
まず、私の事務所の近辺である入善町・朝日町から
以下の通りです。
入善町
• 入善町舟見山自然公園: 標高約300mの舟見山山頂にある自然公園です。春には約500本のソメイヨシノが咲き誇り、富山湾や立山連峰を一望できる絶景とともに桜を楽しめます。山頂までは車でアクセスできます。
• 入善町まちなか桜並木: 入善駅周辺の道路沿いに続く桜並木です。比較的アクセスしやすく、気軽に桜を楽しむことができます。
• 入善町総合運動公園: 広大な敷地を持つ運動公園で、春には園内の桜が美しく咲き誇ります。スポーツ施設と合わせて家族で楽しむことができます。
朝日町
• 宮崎海岸(ヒスイ海岸)の桜並木: 美しい砂利の海岸線に沿って桜並木が続いています。青い海と白い砂利、そしてピンクの桜のコントラストが印象的です。散策をしながら桜を楽しむことができます。
• 朝日町文化交流センター「タラソピア」周辺: 文化交流センターの周辺にも桜が植えられており、施設利用と合わせて楽しむことができます。
• あさひ舟川「春の四重奏」周辺: 少し足を伸ばすと、春にはチューリップ、菜の花、桜、そして残雪の立山連峰という美しい四重奏が見られることで有名な場所があります。桜の時期には、この風景の一部として美しい桜を楽しむことができます。
特に、あさひ舟川の「春の四重奏」は、全国的にも有名になり、観光バスが県外からもたくさん来ていました。
次に、青森県の桜の名所
東北地方には、息をのむほど美しい桜の名所がたくさんあります。
青森県
• 弘前公園: 弘前城を囲むように約2,600本の桜が咲き誇り、「日本さくら名所100選」にも選ばれています。特に、外濠を埋め尽くす「花筏」は絶景です。
o 見頃:例年4月中旬~5月上旬
o 夜桜ライトアップ、弘前さくらまつり開催
次に北海道
北海道は本州と比べて桜の開花時期が遅く、ゴールデンウィーク頃に見頃を迎える場所が多いのが特徴です。
北海道の主な桜の名所
• 五稜郭公園 (函館市): 星形の特異な地形を持つ五稜郭は、約1,600本のソメイヨシノが咲き誇る桜の名所です。箱館奉行所の復元された建物と桜のコントラストが美しく、展望台からの眺めも素晴らしいです。
o 見頃:例年4月下旬~5月上旬
o 夜桜ライトアップあり
• 松前公園 (松前町): 「日本さくら名所100選」にも選ばれている、北海道を代表する桜の名所です。早咲きから遅咲きまで約250種、1万本以上の桜が咲き、長い期間桜を楽しめます。松前城との調和も見事です。
o 見頃:例年4月下旬~5月中旬
o 松前さくらまつり開催
• 円山公園 (札幌市): 広大な敷地を持つ自然豊かな公園で、約1,600本の桜が咲き誇ります。隣接する北海道神宮の参道も桜並木が美しく、合わせて散策するのがおすすめです。
o 見頃:例年4月下旬~5月上旬
o 夜桜ライトアップあり
以上幾つか紹介しましたが、これからゴールデンウイーク。機会があれば、花見の観光を付け加えてはいかがですか!

大相撲大阪場所を振り返って!
大相撲春場所は23日、大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)で千秋楽を迎え、東大関の大の里(24)(本名中村 泰輝(なかむら だいき)、石川県津幡町出身、二所ノ関部屋)が3場所ぶり3度目の優勝を果たした。大関昇進後初優勝となる。
優勝決定戦で高安(右)を送り出しで下した大の里(23日)=田中秀敏撮影
結びの一番で大関琴桜を寄り切って12勝3敗とし、3敗で並んだ高安との優勝決定戦を送り出しで制した。
以上読売新聞オンライン記事よりの抜粋であるが、今場所は、高安が10日目大の里を寄り切りで破ってからは単独トップとなり今場所こそは高安の優勝かと思ったが、千秋楽にその予想は大きく崩れ結果は、大の里の逆転優勝。
勝負の世界は、確かにやってみなければわからないというのが実際のところではないかと改めて思った次第ですが、高安はどうして、ここ一番の勝負所で負けてしまうのか、外貌的には、相手を威圧するような風貌ではあるが、残念ながら蚤の心臓のような繊細な部分が見えてしまうのは残念である。
とりあえず、そうは言いつつも35歳ではあるが、まだまだ、いけそうな感じはしている。
考えてみれば、40歳の玉鷲が今場所も10勝5敗と二けたの勝ち星をあげていることを考えれば、高安もまだまだ頑張れるのではないかと思う。
昨日は、大相撲大阪場所千秋楽の実況をテレビで観戦していたが、高安の地元の市役所では、すごい熱気とともに高安の優勝を信じて、熱い声援を送っているのを見ると、感情的には、高安に優勝してもらいたいと思ったことも事実であるが、
大の里にしてみれば、ここで優勝するかしないかは、横綱昇進を考えた場合何としても優勝をしたいという思いは強かったと思う。
それぞれの思惑でもって臨んだ千秋楽の一戦。勝負の世界の厳しさを改めて感じた次第ではある。
ここでその他の結果を見てみたいと思う。西14枚目の美ノ海は、11勝4敗と好結果を残したが、14日目の高安を破ったのが大きいと思う。ウクライナ出身の安青錦も11勝4敗と好結果を残している。幕尻18枚目の時疾風も千秋楽までは、優勝戦線に名を残しているのは立派だと思う。
若元春、若隆景の兄弟力士も前頭筆頭でともに9勝6敗。来場所の三役入りが期待される。関脇大栄翔は千秋楽の一戦沖縄出身の美ノ海に敗れて、9勝6敗。残念ながら大関とりは出直しの結果に終わったように思う。
最後に郷土力士の朝乃山の話をしたい。今場所は三段目での勝負になったが、結果三段目優勝。来場所幕下15枚目以内なら十両への復帰が可能となる。来場所は、東京両国国技館で5月11日初日、5月25日千秋楽の予定。今場所に劣らず、熱戦を期待したい。

ツバキ(椿)について!
毎朝聞いているスズキ・ハッピーモーニング 羽田美智子のいってらっしゃい。今月2月3日の週は、ツバキ(椿)がテーマでした。
そこで今回はツバキについて話をしてみたいと思っています。なぜ私が、今回このテーマを話題にしたかというと、学生時代に友人と二人で、伊豆大島へ旅行した思い出があり、その旅行の思い出が今も新鮮な記憶として残っているからです。
当時は、貧乏学生で、毎日アルバイトの連続で、この旅行をとても楽しみにしていました。と言って、計画的な旅行ではなく、宿泊先と交通の関係を旅行雑誌かなんかで見て大雑把な感覚で伊豆の旅行をした覚えがあります。
宿泊先は当時学生がよく利用したユースホステルを利用したと思います。ユースホステルでは、宿泊者同士の交流があり、それはそれで楽しかったように思います。
この伊豆大島での記憶で一番記憶に残っているのはツバキがとても鮮やかできれいだったことです。
伊豆大島では、毎年1月下旬から3月下旬にかけて椿祭りが開催されますが、今年の開催で70回目の節目を迎えます。椿まつりは、島を彩る椿の花とともに、一足早い春の訪れを楽しむ、島をあげての一大イベントです。
第70回のテーマは「椿と巡る風土」。椿を愛でるだけでなく、島民と椿が育んできた暮らしの風景や、人々と自然がともに歩んできた「生きている地域の姿」から垣間見る、その土地ならではの風土を感じていただける機会となればということがうたい文句になっています。確かに私が、今現在、伊豆大島でイメージするのは、三原山に象徴されるように火山島であること、やぶ椿が島内に群生していることだと思う訳ですが、
学生の当時はそういうイメージではなく、伊豆半島を巡って、フェリーに乗り伊豆大島へ向かう船旅、これが楽しみの一つだったように思います。
そういう思いを持ちながらこの番組を聞いていたわけですが、折角の椿に関するこのテーマ。最後に椿についての由来や種類について話をして締めたいと思います。
このツバキ。なんと原産地は日本。一般的にツバキというと日本に自生しているヤブ椿のことを指すそうです。由来は代表的なものとしてツバキの葉がツヤツヤしていることから艶やかな葉の木というところからきているそうです。
次にツバキの種類についての話になりますが、ツバキの品種は日本国内だけでも2000以上あるそうです。その中でも一般的にツバキと呼ばれているのは、日本に自生しているヤブ椿のことだそうです。
そんなツバキの中でいくつか紹介すると、例えばユキツバキ。東北や北陸などの雪が降る地域で育つのが特徴です。特に新潟出身の小林幸子が雪椿として歌っていました。
続いてワビスケツバキ(侘助椿)茶道の茶室に飾られるお花、“茶花(ちゃばな)”として、古くから知られています。
名前の由来ですが、一説には茶人・千利休に仕えて、この花を育てた庭師の『侘助(わびすけ)』にちなんだ・・・といわれています。
最後に乙女ツバキ。淡いピンク色をしていて、“ピンクのツバキの代表”ともいえる品種です。日本だけでなく、海外でも人気が高いそうです。
以上思いつくままに話を進めましたが、学生時代に伊豆大島に旅したときの椿の新鮮な色鮮やかな印象が忘れられず今回の話題にしたところです。

大相撲初場所を振り返って!
大相撲初場所は千秋楽の26日、大関・豊昇龍が12勝3敗で並んだ3人による優勝決定戦を制し、おととしの名古屋場所以来となる2回目の優勝を果たしました。
大相撲初場所12勝3敗で並んだ3人による優勝決定戦を制し2回目の優勝を果たした大関・豊昇龍について、日本相撲協会は横綱昇進に向けた臨時理事会の開催を決めたということです。
相撲協会は、今月29日の理事会に先立ち、27日横綱審議委員会に豊昇龍の横綱昇進を諮問しますが、横綱審議委員会の議論の行方が注目されます。
初場所の優勝争いは、14日目終了時点で2敗の金峰山、3敗の豊昇龍・王鵬の3人に絞られていましたが、千秋楽で金峰山が王鵬に敗れ、豊昇龍が琴櫻に勝ち、3人が12勝3敗で並んだわけですが、優勝決定戦は「ともえ戦」で行われ、豊昇龍が金峰山、王鵬に連勝し、名古屋場所以来2度目、大関昇進後初の優勝を果たしました。豊昇龍は今場所、横綱昇進を目指していましたが、途中3敗。しかし、終盤に6連勝し逆転優勝を決めました。横綱照ノ富士の引退や上位陣の不振で波乱の展開となった今場所は、大関が最後に実力を発揮し、千秋楽を締めくくりました。
豊昇龍 横綱昇進に向け臨時理事会開催へ
大相撲初場所で2回目の優勝を果たした大関・豊昇龍について、日本相撲協会は横綱昇進に向けた臨時理事会を今月29日に開催することを決定しました。これに先立ち、27日に横綱審議委員会で昇進の可否を諮問します。
豊昇龍は先場所、13勝2敗で準優勝し、今場所は途中3敗を喫するも終盤6連勝し、12勝3敗での優勝決定戦を制しました。審判部はこの成績を評価し、理事長に臨時理事会の開催を要請しました。
横綱昇進には「大関で2場所連続優勝」が原則ですが、豊昇龍は条件を満たしていないため、昇進には横綱審議委員会で3分の2以上の賛成が必要となります。今後の議論の行方が注目されています。以上が、NHK昨夜10時12分のニュースからの引用になります。
今場所は、琴桜、豊昇龍の同時横綱昇進を期待していましたが、残念なのは琴桜の意外な結果である。連続優勝、横綱昇進のプレッシャーに負けたのか今場所は惨憺たる結果になったのは非常に残念ではあるが、これで終わりではないので、来場所以降の奮起を期待したいと思っている。
豊昇龍については、9日目までに6勝3敗。それも平幕相手の3敗普通ならここで崩れるところよく持ちこたえたと思う。それは、横綱昇進への執念ではなかったかと思う。ここに琴桜との差が出たのではないかと思う。琴桜の内容を見てみると、序盤での1勝5敗の内容は、正代、熱海富士との過去の対戦成績を見ても負けるはずのない戦績であるにもかかわらず無気力な相撲にしか見えなかった。改めて来場所以降の奮起を期待したい。
その他の力士については、金峰山は、14日目までは、単独トップで千秋楽での優勝が決まるのかと思ったが、千秋楽での王鵬 戦で敗戦となり優勝決定戦になったが15日間よくやったと思う。一方王鵬についても今場所の内容を見る限り、相当実力をつけているような感じがした。来場所以降大関候補として頑張って欲しい。
その他の活躍した力士としては、霧島、大栄翔、尊富士が挙げられるが、大の里も大関として、来場所以降に期待したい。相撲ファンとしては、来場所も好取組を期待している。

お正月に関する雑学&豆知識クイズ!
今回は、正月の運試しということで、クイズ10問を出したいと思います。貴方は、いくつ正解できるかな!
第1問
1月10日はなんの日でしょう?
① 110番の日
② 移転の日
③ 福袋の日
第2問
1月21日は「料理番組の日」です。
イギリスのテレビで料理番組の放送が開始されたことが由来で、第一回放送はある料理が放送されました。
ある料理とはなんでしょう?
① ケーキ
② カレー
③ オムレツ
第3問
世界の珍しい成人式クイズです♪
バヌアツ共和国のペンテコスト島では、変わった儀式を成人式にします。
どんな成人式が行われているでしょうか?
① バンジージャンプ
② 寒中水泳
③ 20kmマラソン
第4問
パプアニューギニアの成人式で、成人になるための儀式としてある動物の模様を体に、彫り込みます。何の模様でしょう?
① ライオン
② ヘビ
③ ワニ
第5問
千葉県浦安市では、ある人気なところで成人式を行います。それはどこでしょう?
① 東京タワー
② サンリオピューロランド
③ ディズニーランド
第6問
1月22日はなんの日でしょう?
① から揚げの日
② カレーの日
③ ウィンナーの日
第7問
1月23日はなんの日でしょう?
① 落花生の日
② マカダミアナッツの日
③ アーモンドの日
第8問
1月の歌クイズです♪
「もういくつ寝るとお正月~」が歌い始めの、「お正月」の歌の二番の歌詞「お正月には まりついて おいばねついて 遊びましょう」のおいばねとはなんの道具をつかうものでしょう?
① めんこ
② すごろく
③ 羽子板
第9問
「お正月」の歌を作曲した人は誰でしょう?
① 山田 耕作
② 坂本龍一
③ 滝廉太郎
第10問
1月の誕生石といえばなんでしょう?
① ガーネット
② トパーズ
③ アメジスト
正解
第1問① 第2問③ 第3問① 第4問③ 第5問③
第6問② 第7問③ 第8問③ 第9問③ 第10問①
以上みんなのお助けNAVIより

大関琴櫻初優勝おめでとう!
新横綱誕生なるか。大相撲九州場所千秋楽(24日、福岡国際センター)、大関琴桜(27=佐渡ヶ嶽)が大関豊昇龍(25=立浪)との相星決戦を制し、14勝1敗で念願の初優勝を果たした。祖父は元横綱の先代琴桜、元関脇琴ノ若の佐渡ヶ嶽親方を父に持つサラブレッドが、ついに覚醒。兄弟子で元大関琴奨菊の秀ノ山親方(40=本紙評論家)は、琴桜の成長を分析した上で、次の初場所(来年1月12日初日、両国国技館)での綱とりに太鼓判を押した。
琴桜が念願の賜杯にたどり着いた。豊昇龍の強烈な突き押しにもひるまず、相手の上手投げも踏ん張って残した。最後は豊昇龍が足を滑らせたところではたき込み。執念で白星をたぐり寄せた。琴桜は「決定戦を経験したり、優勝に近づいても優勝できない場所が続いて苦しい思いもあった。しっかり辛抱してやれば、賜杯を抱けるんだと実感できた。初めての賜杯? 重かったです」とかみしめた。
大関5場所目での初優勝は、祖父で元横綱の先代琴桜と同じ。先代が最後に優勝してから51年ぶりに賜杯を抱いた琴桜は「そろそろ優勝しないと、先代にも怒られると思った」と安堵の表情を浮かべた。佐渡ヶ嶽部屋からの優勝は2016年初場所の大関琴奨菊以来、8年ぶり。V決定の瞬間は、兄弟子で10月に独立した秀ノ山親方も特別な思いで見守っていた。
以上が東スポからの記事であるが、今まで、優勝のチャンスが何度もありながら、優勝できなかったのは、精神的な弱さもあったように思う。しかし、今場所は、立ち会いから、一番一番、その執念を感じ取ることが出来たのは精神的に大きな成長を遂げた証のように感じることが出来た。
その最も印象的な勝負が千秋楽での大関豊昇龍との相星決戦ではなかったかと思う。分の悪い大関豊昇龍に対して、投げは充分に警戒していたと思う。この一番での最大のポイントは、この豊昇龍の投げをしっかりとこらえることが出来たことが最大の勝因であったように思う。いよいよ、来場所は、横綱取りの場所でもある。先代横綱祖父の遺志を継いで、立派な横綱になることを期待したい。
その他の力士の活躍にも少し触れたい。新大関の大の里については、前半は新大関として、それなりに頑張ったのは評価できるが、後半の相撲を見ると、諦めが少し早いような気がする。もう少し、相撲に対する執念を磨いて欲しい。若元春、若隆景の両兄弟はともに10勝5敗の二桁勝利、来場所が楽しみである。
最後にNHK相撲解説者の北の富士さんの話をしたい。横綱千代の富士、現相撲協会理事長である八角親方、元横綱北勝海を育てた北の富士さんの訃報を聞いたとき、とても残念な思いをした。北の富士さんの解説は、とても分かりやすく相撲ファンとしては、大相撲を盛り上げてきた影の功労者ではないかとさえ思っていたので、いつ復帰されるか期待をしていただけにとても残念な気がする。ここに個人を忍んで哀悼の意を捧げたい。
来場所もいろんな意味を込めての場所ではあるが、新しい年の場所として、大いに盛り上げていって欲しい。一ファンとして、これからも大相撲を応援していきたい。

カラオケについて!
最近カラオケを利用する機会がほとんどなく、カラオケについてすっかり忘れていたわけですが、10月21日からの羽田美智子のいってらっしゃいの番組で、このカラオケについての話題が取り上げられていました。
それで、今回はこのカラオケについて話をしてみたいと思います。実はこのカラオケについては、仕事上の関係で、ベトナム、インドネシアの技能実習生の講習の中で、彼らのお国では、日本の歌が結構歌われていて、それが、カラオケの店でよく歌われているということもあって、このテーマを取り上げたわけです。
『カラオケ』とはもともと、日本語と英語を合わせた音楽業界の用語で、
“カラ”は“空っぽ”、“オケ”は“オーケストラ”のことです。つまり“歌のない空のオーケストラ”という意味で、“生の演奏ではない伴奏だけを録音した音源”のことを『カラオケ』というそうそうです。今になって初めてカラオケの意味を知ったというのも不思議な話ですが、一つ勉強にはなりました。
今は放送が終わりましたが、ラジオから流れる歌のない歌謡曲という番組がありましたが、考えてみれば、これもカラオケから発想される番組であったように思います。
このカラオケの歴史はと言えば、1967年(昭和42年)頃、『マイク付き装置』と『テープ』、『歌詞カード』の3点セットを開発した方がいます。その方とは、会社の経営者で発明家の根岸重一(しげいち)さんです。根岸さんは“人に頼らず簡単に伴奏ができ、それに合わせて歌えて楽しめるような文化を日本に、そして世界に伝えたい“という思いからこの3点セットを思い付いたんだそうです。根岸さんが開発した装置は『スパルコボックス』という名前で商品化され、スナックなどに無料で置いてもらっていたそうです。そしてお客さんが歌う時は利用料として“1曲100円”をいただいてその一部をお店に渡していたそうです。
カラオケの装置は更に進化して、『マイク付き装置』と『テープ』、『歌詞カード』の3点セットが、起業家の井上大佑(だいすけ)さんによって発明されます。井上さんは1971年(昭和46年)に『8(エイト)トラックテープ』に伴奏を入れ、再生装置にコインボックスをつけた、その名も『エイトジューク』を開発しました。この『エイトジューク』は“カラオケの原型機”ともいわれていて、このヒットにより井上さんは“カラオケのビジネス化に初めて成功した方”と呼ばれています。
その後もカラオケ装置は映像付きのものから採点機能の付いたもの各種のサービスが追加されて今日に至っています。
私が若いころカラオケは全盛期の時代で、仕事帰りのスナックや宴会ではよくカラオケを利用したことを憶えています。当時は、演歌やフォークソングが主流で、せっせと歌詞を憶えたことを記憶しています。外国人実習生のカラオケを歌う姿を見て、なぜかしら、若いころを思い出したのは、時代の流れかと思いながらこの番組を聞いていた次第です。

雑話 朝ドラ!
朝ドラ名場面スペシャルが昨日夕方放送されていました。朝ドラファンとしては、是非見ておきたい番組だったのですが、途中途中しか見ることが出来ず残念に思っていましたが、ふと頭にひらめいたのは、NHKプラスがあるではないかということで、NHKプラスで索引したところ有ったではないですか。
NHKプラスにも視聴期限があることは知っていますので、なんとか期限内には視聴したいと思っています。
今見た範囲での感想を言うなら、とても懐かしいのと今でも内容的にも新鮮で感動を覚えるものばかりです。
一作一作丁寧に作られていることに感心するばかりでなく、登場する俳優さんも適材適所というか番組にあった俳優さんを選んでいるような気がして、それにも感心するところです。
今、朝ドラは、今年度上半期の番組が終了して、後半の番組がスタートして、半月ばかりが過ぎましたが、上半期の朝ドラは、虎に翼で、法曹界の話題が中心で、主人公の猪爪寅子が、女性裁判官としての地位を確立するというストーリーは、現代の社会問題にも直結するような内容で見応えがあったように思います。
同時に私は、朝ドラはBSで見ているわけですが、再放送の方は、オードリーが放送されていて、戦後の映画・テレビの歴史を背景に映画監督を目指す佐々木美月の挫折と成長を描いた作品だったわけですが、出演俳優に大竹しのぶ・長島一茂・舟木一夫を配するなど出演俳優にも気を配った内容は、とても面白かったです。
最後に下半期の朝ドラは、おむすび、再放送の方は、カーネーションの番組ですが、朝7時15分からは、カーネーション、7時半からはおむすびを見ています。都合で見れない場合は、予め録画予約をして同日中に見るようにしています。
カーネーションの方は、今でもあらすじを憶えていて、デザイナーのコシノ三姉妹の母親小篠綾子をモデルにした作品で、岸和田を舞台に繰り広げられる物語は今後も楽しみにしています。
虎に翼の後の作品はおにぎり。この作品も第3週まで終わりましたが、栄養士を目指すヒロインの性格は明るく、ドラマの内容がギャルという設定、それでいて、悪いことはしない明るい友人同士という内容にも好感を持っています。上半期の虎に翼ほどのインパクトはないにしても、私は好感を持ってみていきたいと思っています。

大の里優勝おめでとう!
14日目に2度目の優勝を決めた関脇・大の里は関脇・阿炎に引き落とされ、13勝2敗で終えた。白星締めはならなかったが、大関昇進目安とされる「三役で直近3場所合計33勝」を上回る34勝を挙げた。番付編成を担う審判部は、昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長(元横綱・北勝海)に要請し、受諾された。理事会で昇進が見送られた例はなく「新大関・大の里」誕生が確実となった。九州場所は11月10日に福岡国際センターで初日を迎える。
千秋楽の取組まで崩すことがなかった大の里の表情が、やっと緩んだ。「いい15日間だった。やっと終わった。優勝という結果で終われて良かった」。土俵下の優勝インタビューで、大関昇進が事実上決まったとの吉報を知らされると「まだたくさん稽古して、上に向けて頑張りたい」と意気込み、館内を沸かせた。
秋場所を締める一番では、前に出たところを阿炎に引き落とされた。「14勝したかった。次に向けての課題にしたい」。師匠・二所ノ関親方(元横綱・稀勢の里)の現役時代の最多勝利14勝に並べず悔やんだが、堂々の13勝2敗。三役で直近3場所合計34勝となり、番付編成を担う審判部は打ち出し後、八角理事長に昇進を審議する臨時理事会の開催を要請。初土俵から所要9場所、昭和以降最速の新大関昇進が決まった。
192センチ、182キロで圧倒的な馬力を持つ大器に期待されるのは大関ではなく、その先だ。先場所までの右差しに加え、今場所は相手の右を封じて上体を浮かせてしまう強烈な左おっつけも光った。八角理事長も「立派。前に出ている。天性のような馬力がある」と絶賛した。九州場所、来年初場所と優勝、またはこれに準ずる好成績を残せば初場所後、昭和以降では羽黒山、照国の所要16場所を抜き、11場所での最速横綱昇進の可能性も十分だ。
大関昇進伝達式は25日を予定。「大いちょうは(まだ)結えない」と史上初めて、ちょんまげ姿で臨む。「優勝の余韻に浸っていい報告が聞きたい」としながら、「番付が発表されたら、さらに高みを目指して頑張りたい」とも言った。すぐにでも綱を締める素質を備えた24歳。「強いお相撲さんになる」。夢の実現に向けて歩みを止めることはない。(山田 豊)
以上がスポーツ報知のニュースであるが、優勝インタビューの中でも述べているとおり、大雨被害を受けた地元石川にとっては、この上ない明るい話題となったのではないかと思う。
次に今場所を振り返って簡単に感想を述べてみたいと思う。何よりも残念なのは両大関の結果についてだと思う。大関琴櫻、大関豊昇龍ともに8勝7敗とともに勝ち越すのがやっとで大関としての責任を果たしたとは到底思えない結果で終わったのは、非常に残念である。一方元大関霧島は、12勝3敗の好成績、最後まで優勝争いに絡んでいたのは、大きく評価できる。首のけがも良くなり、霧島本来の相撲がとれるようになったのは大きい。
来場所以降の成績次第では元大関の魁傑以来の大関復帰も可能だと感じる。特筆すべきは若元春、若隆景兄弟の成績かと思う。若元春11勝4敗、若隆景12勝3敗の準優勝はさすがに立派な成績だと思う。来場所以降の活躍が期待される。
最後に十両優勝の尊富士について感想を述べると、やはり、素質は十分で来場所の幕内復帰も充分に考えらるので、来場所の幕内の取り組みを期待している。相撲ファンとしては、いろんな意味で好取組が期待されそうなら来場所を楽しみにしたい。
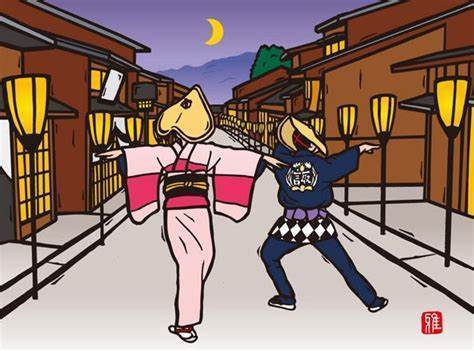
盆踊りについて!
盆踊りは日本の伝統的な夏の行事であり、地域ごとに異なる踊りや祭りが行われています。今回は盆踊りの目的や歴史を簡単に紹介しながら、盆踊りについて話をしてみたいと思います。
そもそも盆踊りの目的はというと盆踊りは、先祖の霊を供養するための行事として始まったわけですが、古代日本の宗教儀式に由来し、死者を敬う心が込められているそうです。
その盆踊りの歴史はどうかというと、盆踊りの起源は平安時代にさかのぼり、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)に関連しているそうです。この盆踊り室町時代には庶民の間に広まり、江戸時代には全国に普及しました。
この盆踊り、現代においては、地域コミュニティの結束を深めるためのイベントとしても重要になっています。住民が一堂に会し、踊りを通じて交流を深める場となっていますが、地域によっては段々と規模が縮小される地域も出てきています。
日本の3大盆踊りと言えば、
西馬音内の盆踊り(にしもないのぼんおどり)
郡上踊り(ぐじょうおどり)
阿波踊り(あわおどり)
以上が代表的なものですが、富山県的にはおわら風の盆が全国的には有名な盆踊りになります。
このおわら風の盆について簡単に紹介すると、富山市八尾町で毎年9月1日から3日にかけて行われる伝統的な祭りです。この祭りは、静かな雰囲気と優雅な踊りが特徴で、三味線や胡弓の音色に合わせて踊られる「おわら踊り」が見どころです。踊り手は浴衣姿で、提灯の明かりが揺れる夜の街を練り歩きます。
おわら風の盆は、五穀豊穣や風災除けを祈願する行事として古くから続いており、その静かな美しさから日本全国から多くの観光客が訪れます。また、夜通し続く踊りは、幻想的な雰囲気を醸し出し、見る人々を魅了します。
さて、わが町の盆踊りと言えば、私も以前はお宮の境内や、小学校の運動会で踊っていた盆踊りがありますが、その盆踊りの名称がよくわからないのでネットで調べたら笹川盆踊りということで、富山県東部の入善町や、朝日町で踊られている盆踊りになります。
今はすっかりその盆踊りも聞かれなくなっていますが、わが町内でも入善駅前で毎年演じられていたのを今は懐かしく思います。

大相撲名古屋場所を振り返って!
大相撲名古屋場所は28日、愛知県体育館で千秋楽を迎え、横綱照ノ富士(32)(伊勢ヶ浜部屋)が3場所ぶり10度目の優勝を決めた。結びの一番で大関琴桜に敗れて12勝3敗となり、幕内隆の勝に並ばれたが、優勝決定戦で隆の勝を寄り切った。
以上が名古屋場所の結果であるが、10日目まで負けなしの10連勝。後続に3差をつけて文句なしの優勝間違いなしと思っていたが、11日目関脇大の里に初黒星を喫してから、14日目隆の勝、千秋楽琴桜と連敗を喫し、結局優勝決定戦で、ようやく隆の勝に勝って10度目の賜杯を掴んだが、一時の勢いが最終盤に陰りを見せたのはやはり体力的な問題があるのではないかとの印象を受けた。
その他の結果としては、隆の勝の活躍が光った。序盤4勝3敗とまさか優勝決定戦にまで進むとは思ってもみなかったが、中日8日目に元大関の御嶽海に勝ってから千秋楽まで連勝し、結果12勝3敗の好成績を生んだのが目についた。確かに力がついてきているのは間違いないと思われる。
先場所優勝の関脇大の里は、序盤5日目まで2勝3敗と先行きが心配されたが、終盤全勝の横綱照ノ富士に勝ってから勢いを取り戻し9勝6敗の殊勲賞、残念ながら10勝に至らず、大関再挑戦は振出しに戻ったが、実力は全勝の横綱照ノ富士に勝ったことにより証明されているので、来場所以降に期待したい。
技能賞を受けた小結平戸海については、よくこの位置で10勝をあげたなと感心している。
初めての三役で二けた勝利は、さすがに自力がついてきたのかと思う。来場所以降もこのような成績が持続するなら楽しみな存在だと思う。
それと、再入幕の若隆景については、11勝4敗と優勝経験があり、一時は大関候補と目されていたが、ケガにより、幕下まで降格していたが、ようやく体調も復帰し兄若元春とともに幕内上位での活躍、大関候補として、来場所以降の活躍を期待したい。
最後に、郷土力士の朝乃山についての話であるが、序盤3連勝と期待を以て見ていたが、4日目一山本との対戦で左膝の前十字靱帯(じんたい)断裂の負傷を負い、回復までには1年はかかる見込みとのこと。やむを得ない結果であるが、ケガをしっかり治して、再起にかけて欲しい。以上が大相撲名古屋場所を振り返っての私の感想である。
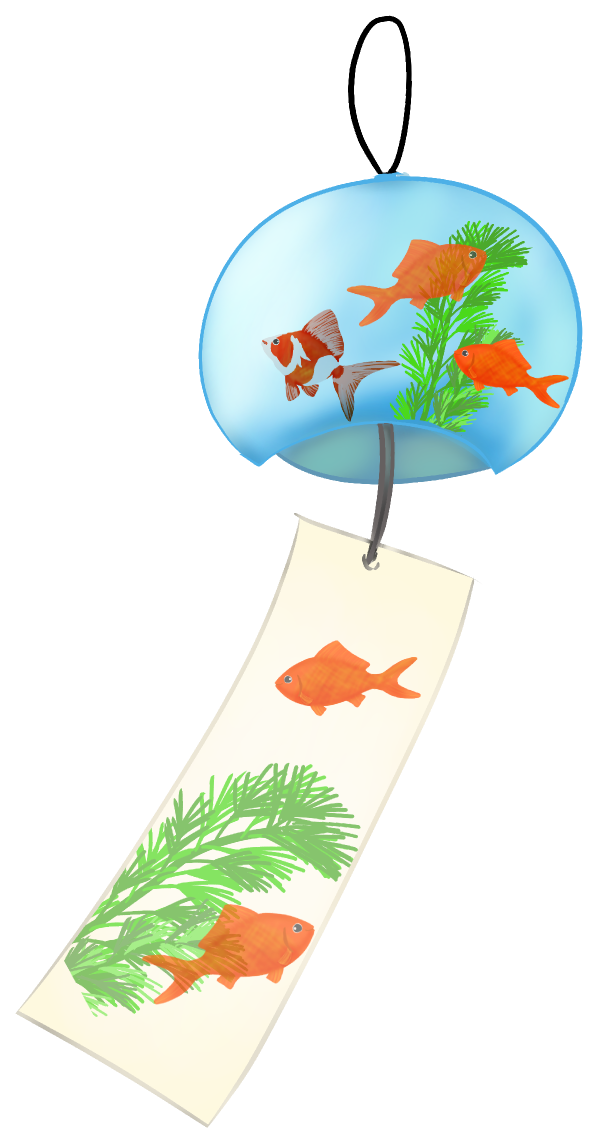
五感の涼について!
毎日暑い日が続いています。地球温暖化のせいか私の子供時代に比べて夏がひと際熱くなったような気がします。そこで今回は五感の涼について話をしたいと思っています。
昨今エアコンが普及したせいか、暑いと感じると熱中症対策として、エアコンを使う頻度が増してきたように思います。健康のためには、確かにそれはそれでいいのかもしれませんが、昔と比べて風情がなくなったように感じます。それは、五感で感じる涼しさとは根本的に違うものだからかもしれません。
ただエアコンは猛暑が続く今日では必要不可欠なものであると思う訳ですが、子供のころに感じた涼しさとは違う涼しさではないかと思う訳です。
例えば、チリンチリ~ン♪と鳴る、風鈴の音や、すだれなど五感で感じる涼しさはエアコンで感じる涼しさとは少し違うような気がします。それは、心で感じる涼しさというか、エアコンのように体で感じる涼しさと違うからなのかもしれません。
そこで、この五感の涼について、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の順で話をしていきたいと思います。
まず、視覚についてですが、金魚鉢、すだれ、蚊帳などがありますが、金魚鉢は本当に目で見て涼しいと感じるものではないですか、すだれ、これは子供のころすだれを夏になるとよく居間の境につるしたものです。それから蚊帳、夏の暑いときこの蚊帳を寝床に吊るして、この蚊帳を持ち上げて寝床に入ったことを覚えています。
次に、聴覚についてですが、先ほども述べた風鈴が代表的なものですが、その他に水琴窟などがあります。音で聞いて涼しさを感じるのは風鈴が一番かと思います。あのチリンチリ~ン♪と鳴る、風鈴の音この音を聞いただけで涼しさを感じるのはどういう訳でしょうか。
次に、触覚についてですが、例えば、井戸水の音、子供のころ私の家でも井戸を使っていた記憶がありますが、あの深い井戸から水をくむとき桶が深い井戸に届いたときの音は本当に冷たい感じがしたのを覚えています。
それと、夏の暑い日、私の家は雑貨屋だったわけですが、お店の前の道路に打ち水をした時の涼しさは本当に涼しさを感じたものです。
次に嗅覚で感じる涼しさですが、夕立の匂いが、まさに嗅覚で感じる涼しさだと思う訳です。暑かった日中の厚さが夕立が去った後のあの匂い、いっぺんに、あたりが涼しくなったように感じたものです。
最後に味覚による涼しさですが。ラムネやかき氷、などが代表的なものかと思います。その他にもところてんや、ソーメンなどがありますが、いずれにしても食べて涼しさを感じるわけですが、見ただけでもこれらの食品は涼しさを感じるのは味覚の他に視覚も合わさって余計涼しく感じるからなのかもしれません。
以上五感による涼しさを話した中で、最近のエアコン中心の涼しさだけではなく、五感で感じる涼しさも再認識した中で、この猛暑を乗り切っていきたいものだと感じています。

羽田美智子のいってらっしゃいより、クセについて!
毎日朝の時間に聞くとはなしに聞いているのが、スズキ・ハッピーモーニング羽田美智子のいってらっしゃいのラジオ番組です。わずか5分間の番組ですが、日々の習慣として聞いています。
最近はラジコもあるので聞けない時は、ラジコで聞いたりもしています。内容は1週間ごとに変わりますが、6月10日の週は、クセについての話題がテーマになっていました。
このクセについては、なるほどと思う内容でもあったので、今回は私のクセも含めてこの話題を取り上げてみたいと思います。
6月10日(月)については、クセとはどういうものか、或いは、クセとはどういうメカニズムで出るのかということを分かりやすく解説していました。それによると、クセとは無意識に出てしまう好ましくない言葉や行動のことで、何らかのストレスが原因でそのクセが出るそうです。
このクセは自分では気づいていないことが多いそうで、まずは“自分にどんなクセがあるのか”、そして“そのクセを周りの人がどう感じるか”を知ることが大事だということを話していました。
確かに自分のクセは他人から指摘されて初めて気が付くということが多いかもしれません。実はこの放送を聞いて、自分にはどういうクセがあるのか改めて考えてみました。例えば、人と話をするとき、相手の話をよく聞いてから間を置いて自分の話をしたらどうかと家族から言われたりすることが結構よくあります。一時はムッときますが、私の悪いクセを直そうと思って、指摘してるんだと今は良い意味で理解しています。
このクセについては、火曜日は、『髪の毛をさわるクセ』水曜日は、『貧乏ゆすり』木曜日は、『クチぐせ①』金曜日は、『クチぐせ②』というように人にはいろんなクセがあるものだと改めて感心した次第です。
その中でも、貧乏ゆすりは結構目にすることがありますが、人ごとだと思って、何となく良いクセではないなと勝手に思ったり、クチぐせの中でも話の途中で『えー』とか、『あの~』とか言うクチぐせは、私も気がつかないうちに使っているような気もします。
その他にも金曜日の、『クチぐせ②』では、『だけど』や『でも』、『だって』がクチぐせの場合、“すぐに言い訳をする”、“人の意見やアドバイスを聞こうとしない”と見られてしまうので、直した方が良いクセだと説明されていました。
こうやって見ると一般的にクセと言われるものには、悪いクセが圧倒的に多く、人に与える印象もあまり良くないことが多いと感じたことです。これを機会に悪いクセについては自分なりに気を付けたいと思ったところです。

大の里優勝おめでとう!
新小結大の里が阿炎を破って12勝3敗で初優勝を果たした。初土俵から所要7場所目の初V。今年春場所の尊富士の10場所を上回る史上最速で、幕下付け出しでも1972年夏場所の輪島の15場所目を上回る史上最速優勝となった。
師匠の二所ノ関親方(元横綱稀勢の里)は、茨城県つくば市内の祝賀会場で大の里の取組を見守り、会場入り口で弟子を出迎えて優勝の報告を受けた。
部屋を創設してから初の幕内優勝に「まさかこんなに早くこの日を迎えるとは思っていなかった」と喜び、「本当によく大の里が頑張ってくれた」と感謝。初土俵から所要7場所での初優勝には「僕からしたら考えられない」と思わず苦笑い。自身は初土俵から89場所目での初Vだった。「すごいスピードだと思います」と驚きを隠さなかった。
大の里については「精神的にだいぶ成長している。腰も少しずつ安定してきて、日頃の基礎の鍛錬が出ている。体圧をしっかりとかけられている。突き押し力士にも馬力負けしないところが、今日の阿炎戦も良かった」と称賛した。
その上で「もっと腰が下りて、基礎体力ができたらこんなもんじゃない」と、さらに大きく伸びることを示唆。「四股踏みとかが楽しくなってきたら横綱になれるんじゃないか」と期待を込めていた。
以上デイリースポーツ記事からの参照であるが、入門からわずか1年での優勝は将来の大器を伺わせるに十分な実力を備えているといって過言ではないように思う。私は石川県出身力士の横綱輪島が好きであったが、大の里の性格は何となく明るい感じ或いはものに動じないところが輪島によく似ているような気がする。
今後の取り組みについては、二所ノ関親方の指導をしっかりと受け止めて、基礎から再度しっかりと取り組んでほしい。そうすれば横綱も近づいてくると思われる。
次に今場所の内容を振り返ってみると横綱照ノ富士については、ケガによる負傷が段々と致命的になっているような気がする。大関の貴景勝もケガから立ち直れていない感じがする。霧島も来場所は関脇からやり直しの状況だが10勝すれば大関に復帰するので来場所は頑張って欲しい。
その中で大関琴桜、豊昇龍はかろうじて責任を果たしたような感じではないかと思う。前頭西筆頭の大栄翔、関脇阿炎は、あと一歩のところで惜しくも優勝には届かなかったが、来場所以降精進してほしい。
最後に郷土力士の小結朝乃山は、今場所もケガによる休場で、残念な結果に終わったが来場所以降ケガを克服しケガに負けない身体づくりをしっかりやって欲しい。
相撲ファンとして、来場所以降も力のこもった取り組みを期待したい。

朝ドラ 虎に翼!
朝ドラ「ブギウギ」が終わって、「虎に翼」が始まってから早2週間が経過しました。朝ドラファンとしては、新しい朝ドラはどういった内容か楽しみにしていた訳ですが、2週間見終わった感想としては、とても今後の楽しみな内容だと思いました。
猪爪寅子のモデルになったのは三淵嘉子。日本初の女性弁護士で裁判官、裁判所長になった人です。
現在女性の地位向上を目指す中で女性活躍推進法が制定されるなどあらゆる面での女性の地位向上が図られていますが、戦前の日本或いは敗戦後の日本において男女平等が日本国憲法において保証されたとは言え、まだまだ日本の意識構造の根底には女性差別の風習が色濃く残っていたと思います。
翻って私の幼いころ昭和30年代においても父親の威厳は当たり前でどの家でもそうであったように、父親の意見に逆らうことはできなかったように思います。そんな中で、このドラマの猪爪寅子がどのようにしてそんな社会に対応していくのか楽しみでもあります。
またヒロインを演じる伊藤沙莉さんのこれまでの演技を見ていてもとても人懐っこく愛らしい感じがして、とても好印象を持っています。是非とも前作ブギウギのヒロイン水谷趣里さんのようによい演技を期待したいと思っています。
併せて、私は、朝ドラはBSで楽しんでいるわけですが、今回のオードリーも前作のまんぷくの後を受けての再放送こちらの方も楽しみにしたいと思っています。

尊富士優勝おめでとう!
東前頭17枚目の尊富士(24)=伊勢ケ浜=が、豪ノ山を押し倒しで破り、13勝2敗で優勝を決めた。新入幕力士の優勝は、1914年夏場所の両国以来110年ぶりの快挙となった。
右足首を痛めていた中、テーピングでガチガチに固めて強行出場。豪ノ山を押し倒しで撃破し「気力だけで取りました」と振り返った。前日には宿舎で横綱照ノ富士から「お前ならできる」とゲキを飛ばされた。痛み止めの注射を打ち「昨日の夜は寝られなくてこんなにつらいとは思わなかった。ご飯も入らないし、食べてもおいしくなかった。歩けなくてもうダメだと思った」。それでも「『お前ならできる』と言われた。そのおかげです」と実感を込める。
師匠の伊勢ケ浜親方からは「力はいらねえならやめとけ」と言われたという。それでも「勝っても負けても土俵に上がらないとと思っていた。この先終わってもいい。一生後悔すると思った」と尊富士は気力を振り絞り土俵に立った。そして優勝の2文字をつかんだ。
「本当に優勝したのかなと思った」。勝った後の記憶はなかった。「もう一回やれと言われても無理。気力だけです」というほど追い詰められた中で、価値ある白星をつかんだ。
尊富士は14日目の朝乃山戦で2敗目を喫した際、右足を負傷。千秋楽の出場が危ぶまれたが、右足首をテーピングで固定して土俵に上がった。NHKの中継で解説を務めた師匠の伊勢ケ浜親方は「よく自分から攻めましたね。一瞬前に押して、残されたのでオッと思ったが、その後態勢を整えてまた自分から攻めてよかった」と弟子の相撲を褒めた。
尊富士は「ここからがもっと大事。しっかりケガしない体を作らないと。みんな強かったし、不安もあった」。110年ぶりの新入幕Vから、さらなる高みを目指していく。
以上が、デイリースポーツの今朝のニュースからの引用になります。
ところで、今場所は荒れる大阪場所の通り、横綱照ノ富士の3連敗の後の休場、大関霧島の不調、大関貴景勝の7勝のあとの3連敗13日目の大関琴の若に勝利してようやくカド番を脱出した時点で休場。横綱・大関陣で役割を果たしたと言えるのは、大関豊昇龍と新大関の琴の若の二人だけという結果に終わっている。
この場所を盛り上げたのは、何といっても優勝した尊富士と前頭5枚目の大の里の二人ではなかったろうか。若い二人の来場所以降の活躍を期待したいところではある。
最後に、郷土力士の朝の山の活躍も楽しみではあったが、14日目の尊富士はよい取り組みではあったと思う。寄り切りで勝利した一戦は文句のない勝利であったと思う。
但し、この一戦で土俵際で負傷した尊富士が千秋楽足首をテーピングして優勝したことにより、朝乃山の不安は消し飛んだのではないかと思う。
来場所も観客を沸かせるような好取組を期待したいと願っている。

お彼岸にまつわる話!
今月3月20日は春分の日です。一般に春分の日ということで浮かんでくるイメージは、国民の祝日、昼と夜の時間が同じくなる日等この程度の知識しかないのではないかと思います。
そこで今回は春分の日についてのいわれや、その意味をネットからの知識を検索して考えてみることにしたいと思っています。そもそも春分の日とは、秋分の日も同様ですが、仏教的な意味合い、神道的な意味合いを併せ持つ日本的な行事であるということです。
お彼岸の始まりの物語として、御釈迦様の弟子にあたる目蓮が、あの世へ旅立った母を神通力で見てみると、母親は飢餓に餓え、苦しんでいました。母親はこの世にいた頃に、他人へ物を惜しんだために、餓鬼道に落ちていました。目蓮は疑問に思います。「あの優しく愛溢れる母が、なぜ餓鬼道に落ちたのか。」と。そこで目蓮が御釈迦様に尋ねたところ、御釈迦様はこう答えました。「あなたの母親は、我が子可愛さに他人の子どもや、他の人々への物を惜しんだからです。」といわれたそうです。
そこで目蓮は御釈迦様の教えに倣い、7月15日に修行を終えた修行僧や、多くの人々に食べ物、飲み物を施しました。その徳により自らの母親を、餓鬼道から極楽へ導きました。
これが仏教的な意味合い、一方神教的な意味合いとは、神教では古来から万物に神々がいるとされ、特に太陽神を崇めてきました。そして前述したように、春分の日、秋分の日は、太陽が真東から上がり、真西に沈みます。また、農耕社会であった日本では、種蒔きの頃の春、収穫時期の秋、それぞれに神々に祈った風習が、お彼岸に繋がった、と言う一説もあります。こうした意味合いから、日本独自の考え方が伝わったとされています。
ところで、春分の日にぼたもち、秋分の日にはおはぎを食べる風習はご存じですか、私もその意味は余り深くも考えもしませんでしたが、これは、秋のおはぎは採れたての小豆を使うため小豆の皮が柔らかくそのままあんこに出来たため、ぼたもちは、春時期に作られるので小豆の皮が固くこしあんで作る必要があったからだそうです。いわれてみればなるほどと思う話です。
また、お彼岸に供える花についても注意が必要だそうです。それは、故人に供える供花は三回忌までは、白い花を中心として選ぶようにし、それ以降はこのような制約はないそうです。ただお彼岸に選びたい花としては、アザミや白などの彼岸花、そして薔薇がよく選ばれるそうです。その他トルコキキョウや菊なども人気があるそうです。
如何でしょうか、多少なりともお彼岸について知った上で、お彼岸のお墓参りをするのも悪くはないかもしれませんネ!

久遠チョコレート!
2月14日はバレンタインデーですが、先日カンブリア宮殿で久遠チョコレートが紹介されていました。久遠チョコレートについては、以前から障害者に対して、なるべく障害者としてではなく、普通の従業員に近い状態で雇用することを目指しているということに感銘を憶えこの番組を視聴していたわけですが、改めて久遠チョコレート代表の夏目社長の話を聞いて、納得をしたわけです。そんな意味で、今回はバレンタインデーに因んでこの久遠チョコレートを話題にしたいと思っています。
チョコレートやクッキーの製造販売で、いまや北海道から九州まで40店舗を構える久遠チョコレート。その急拡大の秘密は、生き生きと働く様々な障害を持つスタッフたち。400人を超える障害者に働く場を生み出し、奇跡の成長を遂げる異色のショコラティエ集団の舞台裏に迫る!というテーマで放送されたわけですが、
この放送の詳細内容は以下の通り
絶品チョコ150種類!障害者の年収を10倍にした“久遠の奇跡”とは?
余分な油を加えないカカオ本来の味を楽しむ100%ピュアチョコレートに、様々な食材を混ぜ込んだ独自の味わいで顧客を掴む「久遠チョコレート」。地元の「雲海ほうじ茶」や「次郎柿」など、こだわりの食材をチョコレートにコラボさせ、そのバリエーションは150種類にまで増えた。開業9年で全国に拡大、創業物語が映画になり“久遠の奇跡”とまで呼ばれる理由は、従業員の実に6割が障害者で、しかも彼らの所得を全国平均の10倍にしたからだ。最近では、重度障害者を雇用する工場「パウダーラボ」も稼働。大手企業からも注目を集める久遠チョコ、おいしさを生み出す秘密とは?
「クロネコヤマト」創業者との“衝撃の出会い”が発端!日本唯一のチョコ工房の秘密
創業者の夏目が「障害者雇用」に問題意識を持ったのは20代の時。「クロネコヤマト」創業者・小倉昌男の本で「障害者の平均給与は月1万円」という事実を知り衝撃を受けたことだ。小倉が開業した障害者が働く「スワンベーカリー」を自分も手がけたいと決意。小倉の元を訪ねるが、夏目が店舗さえ持たない若者と知るや「商売をなめるな、帰りなさい」と言い放たれてしまう。そんなきっかけで夏目の挑戦心に火がつき、障害者3人とパン工房を開業する。そして10年の苦難の末「障害者に最も適した仕事は、失敗しても溶かしてやり直せるチョコ作りだ」と久遠チョコレートを立ち上げる。伝説の経営者から商売の厳しさを叩き込まれた夏目は、いかにして“久遠の奇跡”を生み出したのか?
企業のFC店続々!障害者自身が自立できる店作りとは?
日々「久遠チョコレート」の現場を様々な企業が視察に訪れる。現在、久遠チョコはフランチャイズとして手がける企業も生まれているのだ。最近では、ソフトクッキー業態も開業。大手企業も注目する久遠チョコ。次なる展開は?
働くスタッフの約6割が障害者。障害者は「B型事業所」と呼ばれる福祉作業所で働くことが多い。平均工賃は月額1万6千円程度。憤りを感じた夏目さんは「月額1万円」の壁を打破すべく、知的障がいのあるスタッフを3人雇い、ベーカリーを開業。借金を重ねつつ、最低賃金を保障して雇用を守った。「ただし製品化を高めると、ついてこられない人がでる」30代でショコラティエに転身。チョコは当たった。重要なのは、夏目さんが感じた『憤り』だ。いちばん底に怒りがある。底にある怒りは、あらゆる誘惑と欺瞞から本人を守る。
以上放送の詳細を自分流にアレンジすることなく、京セラ創業者の稲森さん流の方法で紹介した訳ですが、私が感心するのは、障害者を障害者として、対応するのではなく一人の大切な人間、社員として、対応しようという、心構えに感心することです。
ともすれば、法律を前提とした、障害者雇用率、或いは、表面的な外面を意識した会社も多い中で、夏目代表は心底、障害者の内面的な生きがいを感じながら久遠チョコレートを続けておられることに共鳴を感じる次第です。
しかも番組内でも紹介があったようにお客様も喜んで久遠チョコレートを求めていることに関心もする次第です。それは、彼ら、彼女らが、久遠チョコレートの職場を愛しており、
日々いかにお客様に喜んでもらえるチョコレート作りに励んでいるかの証ではないかとも思えるからです。今後とも久遠チョコレートの職場作りに注目したいと思っています。

大相撲初場所を振り返って!
大相撲初場所は28日、両国国技館で千秋楽を迎え、横綱照ノ富士(32)が4場所ぶり9度目の優勝を飾った。13勝2敗で並んだ関脇琴ノ若(26)との優勝決定戦を制し、3場所連続休場から復活を果たした。
照ノ富士は昨年夏場所で優勝したが、腰のけがで名古屋場所を途中休場し、秋、九州場所を全休していた。土俵下の優勝インタビューで「けがが良くならずに休場が続いたが、心だけ折れないように頑張ってきたので、よかった」と語った。
初優勝を逃した琴ノ若も大関昇進が確実になった。三役で直近3場所の勝ち星合計が、大関昇進の目安とされる33勝に到達。日本相撲協会の八角理事長(元横綱北勝海)は取組後、琴ノ若の大関昇進を諮る臨時理事会を開催する意向を明らかにした。昇進は31日に正式決定し、3月の春場所は1横綱4大関となる。
以上が読売新聞の今朝のニュース報道内容である。今場所は、横綱・大関陣が安泰の中で、取り組み内容についても見どころのある内容のものが多かったと思う。その中でも、石川県出身の西前頭15枚目新入幕の大の里は、9日目まで8勝1敗と優勝戦線に顔を出すほどの好成績で場所を盛り上げてくれたことには相撲ファンとしては、嬉しい限りだったとおもう。また、能登半島地震による被災者にとっても大いに元気づけられる内容であったのではないかとも思う。
更に嬉しいのは、富山出身の朝乃山においても7日目までは単独のトップで、優勝に大きな期待があったが、残念ながら8日目の対戦相手の玉鷲戦で負傷して休場に追い込まれたのは大きかった。幸い負傷の程度は軽く、13日目から再出場し結果9勝3敗3休の勝ち越しで、来場所の番付予想では前頭筆頭まで復帰する予想が出ており、来場所以降の活躍を期待したい。
今場所優勝には至らなかったものの、13勝2敗の好成績を上げ、来場所の大関昇進が確実になった琴の若については、相撲内容を見ていても確かに強くなったなという感じがしている。優勝決定戦の横綱照ノ富士との対戦を見る限りにおいては、まだまだという感じがしないでもないが、その他の取り組み特に大関霧島との対戦を見ていても先が楽しみな力士ではある。祖父の横綱琴桜を目指して、是非目標を横綱にもって、精進してほしい。
その他では、若元春はさすがに自力がついているのか、2日目の横綱照ノ富士戦では、熱戦の末、横綱照ノ富士に勝利した一番は、好取組であったと思う。あと大関豊昇龍については霧島戦の珍しい技二枚蹴りで敗れて、負傷し休場に追い込まれたのは痛かったと思われる。今場所は、横綱・大関陣が安定しており、楽しみな取り組みが多かったように感じている。是非、来場所も楽しみな取り組みを期待したい。
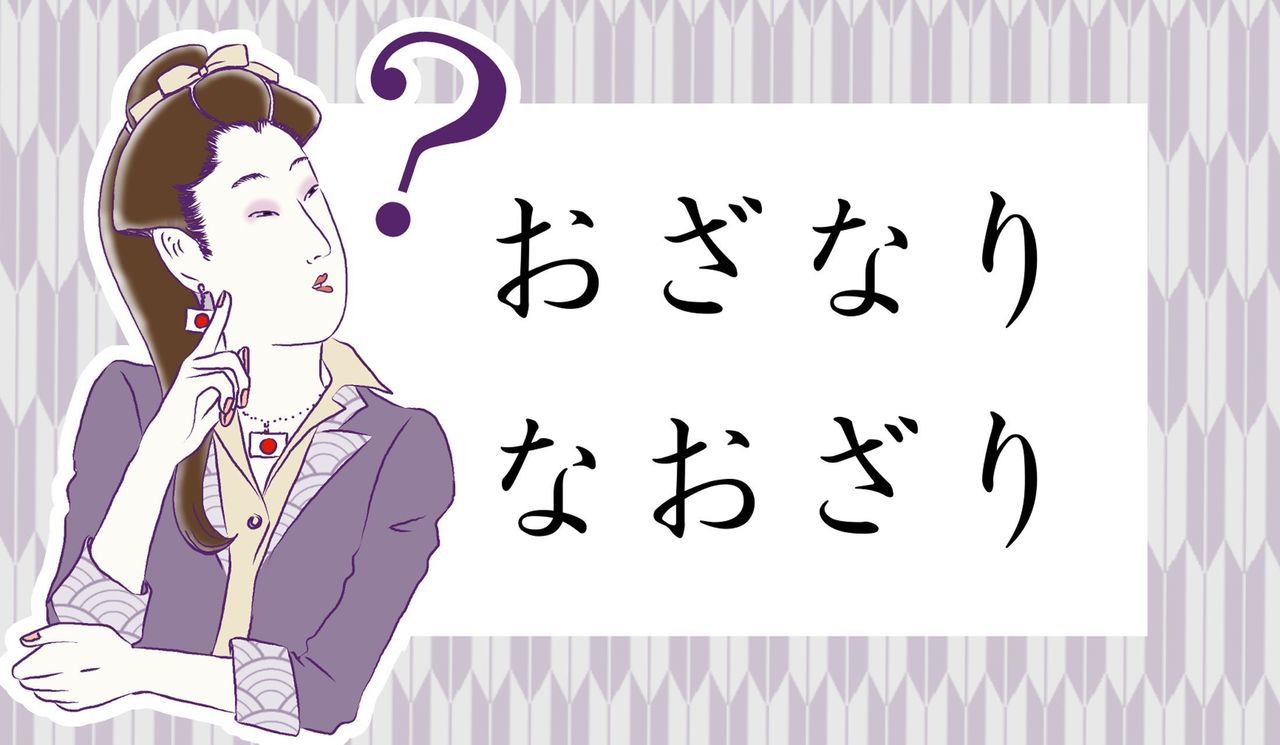
画像の説明を入力してください
間違いやすい言葉!
羽田美智子のいってらっしゃいは、毎朝聞くのが習慣になっていますが、ラジオ番組の編成替えになって以来、放送時間が以前と違ってきているので、最近はラジコでの聴取で、隙間時間に聞くようになっています。
それはさておいて、12月11日からの放送内容は、間違いやすい言葉についてというテーマで放送がありました。この内容については、興味があったので、今回の雑話については、この間違いやすい言葉について、話をしてみたいと思っています。
私たちが日頃、使っている言葉の中には、意味ですとか使い方を間違って使っている言葉が結構あるのではないかと思っています。
そこで放送内容のすべてを紹介すると長くなりますので2点程ピックアップして紹介するとともに、私の感想も織り込みたいと思っています。
まず最初は、おざなりとなおざり。この両方の言葉、何となく普段から使っていますが、そもそも語源が違っているということ。例えば『おざなり』は『御座敷の形・御座敷の形(なり)』という言葉が語源で、“お座敷・宴会の席で、形ばかりを取りつくろったこと”から“いいかげんに物事をすること” という意味でそれに対して『なおざり』は、“そのままで何もしない”という意味の『なほ』と、“遠ざける”という意味の『さり』が合わさってできた言葉とする説があるそうです。
そういった経緯から、同じ“いいかげん”を表す言葉でも、『おざなり』は“内容はともかく、行動は起こして、とりあえず最後までやった”。『なおざり』は“行動さえもしなかった。または行動を起こしても最後までやらなかった”と解釈できるそうです。
これを『お仕事』にあてはめますと、『おざなりなお仕事』の意味は、“仕事はしたものの、内容はいいかげん”。
『仕事をなおざりにした』の意味は、“仕事そのものをしていない、または途中で投げ出した”になるそうです。
もう一つ紹介すると、「信用」と「信頼」という言葉、いずれもどちらの意味も深く考えることなく使っていますが、『信用』には“確かなものと信じて受け入れること”、“信じて疑わないこと”という意味があるそうです。
“お店の信用に関わる”ですとか、“あの人は信用できる”といったように使われます。
それに対して『信頼』には、“信じて頼りにすること”“頼りになると信じること”という意味があります。
“信頼できる先生”ですとか、“消費者の信頼を裏切る”といったように使われます。
このことから『信用』とは、“これまでの行いや実績、成果に対する評価から生まれるもの”。それに対して『信頼』とは、“その人自身の人柄や考え方、言動などの評価から生まれるもの“なのだそうです。
他にもマナーとエチケットなど自分でも区別がつかないで使っている言葉が結構あるもんだと改めて、自分の不勉強仁感じ入った次第です。

大相撲九州場所を振り返って!
大相撲九州場所千秋楽(26日、福岡国際センター)大関霧島(27)が大関貴景勝(27)を突き落とし、13勝2敗で4場所ぶり2度目の優勝を果たした。1差で追っていた熱海富士(21)が敗れて4敗目を喫し、取組前に大関として初の賜杯が決まった。
昇進問題を預かる審判部の佐渡ケ嶽部長(元関脇琴ノ若)は霧島の13勝について「内容もいい相撲で、安定していた。レベルの高い成績じゃないですか」と評価した。
横綱審議委員会(横審)の横綱昇進の内規は「大関で2場所連続優勝もしくはそれに準ずる成績」。9月の秋場所を11勝4敗で制した大関貴景勝は、1場所15日制が定着した昭和24年以降4例目の最低成績に加え、優勝決定戦では立ち合いに変化した内容が指摘され、審判部ではこの九州場所を「綱とり」と明言しなかった。
佐渡ケ嶽部長は、霧島の来年1月の初場所での綱とりに「そうなるでしょう」との見解を示した。初めての横綱昇進に挑む霧島は「自分のできることを全部やって自信をつけて頑張りたい」。横綱の誕生は令和3年名古屋場所後の照ノ富士が最後。同九州場所から、一人横綱が続いている。
以上がサンケイスポーツ新聞の今朝の記事であるが、今場所は、序盤は上位陣も安定した取り口で誰が優勝するのか判断が難しい状況であったが、中日以降次第に優勝候補が縛られてきた感じがする。その中でも異彩を放ったのが、西前頭8枚目の熱海富士ではなかろうか。先場所に続いて、最終盤まで優勝争いに絡んできたのはさすがに自力がついてきている証ではないかと思われる。それと東前頭3枚目の高安。依然として実力は侮れないものを持っているような気がする。最終的には10勝5敗と二けたの勝ち星をあげ来場所での活躍が期待される。
わが郷土力士の朝乃山については、中日より出場し結果は4勝4敗7休の結果であったが、貴景勝に勝った一番、霧島には負けはしたが、惜しい一番ではなかったかと思われる。
いよいよ来場所は、大関霧島の綱取りの場所になるが、今場所の相撲内容を見ていても安定した相撲で、来場所の結果が楽しみになってきている。一相撲ファンとして、来場所もよい取り組みを期待したい。
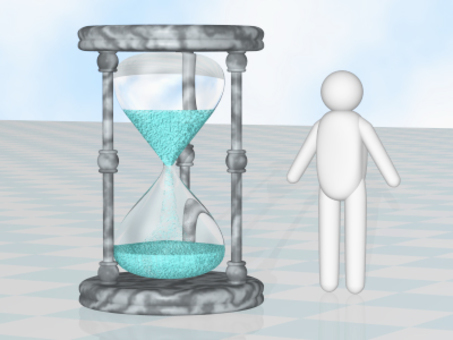
年をとると時間の経過が早く感じる理由!
年をとると皆さん同じだろうと思う訳ですが、時間の経つのがものすごく速いと感じることはないですか?
私自身振り返ってみると、最近特にそう思うようになってきました。還暦を迎えたときは早いものではや還暦かと思ったものですが、古希を終えての現在は階段を転げ落ちるように、時間の速さを感じるようになってきました。この現象について、ネットで検索したところ、ジャネーの法則というものがあって、その法則にしたがえば、このように感じるのだという記述がありました。
そこで今回は、このジャネーの法則についてその内容を確認するとともに、どうすれば、そのように感じないで済むのか、或いは、貴重な時間をどうやって過ごせば、良いのかを考えてみたいと思います。
早速ですが、先ずはジャネーの法則とは何かを見てみたいと思います。
ジャネーの法則とは、心理学者ウィリアム・ジャネーが1960年代に提唱した、時間の知覚に関する法則です。この法則は、「経験の新しさが時間の知覚に影響を与える」という仮説を基にしています。具体的には、新しい経験や情報が多いほど、時間が長く感じられるとされています。逆に言えば、新しい経験が少ない場合や繰り返し同じことを行っている場合は、時間が早く過ぎていくように感じられるというものです。
例えば、子どものころは日々新しい経験や学びがたくさんあります。しかし、大人になると、新しい経験が少なくなることで、ジャネーの法則に基づき、時間が早く過ぎていくように感じられるというのです。
また、大人になると、生活が一定のパターンやルーチンになりがちです。毎日の仕事や家庭のスケジュールが定まっていることで、新しい出来事や経験が少なくなります。このルーチン化が進むことで、時間の経過があまり意識されなくなり、それが早く感じられる要因となります。他にも注意力の低下や、心理的ストレスによってもそのように感じることがあると解説しています。
では、この現象を緩和するためにはどのような方法があるのでしょうか。以下にいくつかの方法が紹介されています。
新しい経験を積極的に追求する。時間の管理方法を見直す。また、スケジュール管理やタスク管理の方法を工夫することで、時間を効率的に使うことができ、より充実した時間を過ごすことができます。その他にも、マインドフルネス練習により、時間が早く過ぎていく感覚を緩和することが出来るとされています。休息を意識的に取り入れたり、友人や家族とのコミュニケーションを大切にし、共有する時間を増やすことによっても新しい経験や情報を増やすことができ、時間の経過を遅く感じることが出来る効果があるとされています。
以上述べたようにジャネーの法則によれば、年齢が経過するほど時間の経過が早く感じられるのはやむを得ないことであると同時に、それに対しての方法もある程度紹介されてはいます。
けれど、時間の経過は現実的には絶対的なものであって、感じ方がどうであれ変わるものではないわけで、であるならば、むしろ大切な時間をいかに有益に過ごせばよいのか、そのことを考える方が大切なのではないかと私なりに考える訳です。
そこで最後に私自身が、日々やっている方法を紹介したいと思います。それは、朝起きてからその日の行動をイメージして大体6項目程度になると思いますが、1枚のメモ帳に書き出すことにしています。そのことにより、少しでもその日の行動を効果的に使えればと思っています。
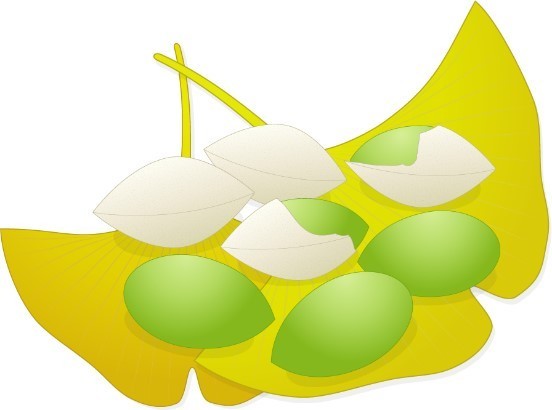
秋の味覚 銀杏について!
今回は秋の味覚、銀杏について話をしてみたいと思います。というのも私は銀杏が大好きで、串に刺した銀杏を肴に、ふろ上がりの冷たいビールを飲んだり、熱燗の酒の肴に食べるのが最高で、それが至福のひと時であったりもするからです。
また、茶碗蒸しに入った銀杏は何となく茶わん蒸し自体を、更においしくさせる一品であり風味付けにも最高なのではないかとも思っています。
そんなわけで今回は銀杏を題材にして話をしようと思った訳です。ところで、この銀杏、いつ頃が収穫の時期なのかということですが、私が何となく今まで思っている時期としては、晩秋の時期、10月から11月ごろ、風の強い日、こんな感じです。というのも、このような感じの日に近くのお寺さんの昔からある銀杏の大木の下に銀杏がたくさん落ちているのを習慣的に感じているからです。
そのような日には、ちょっとした熊手とポリバケツ又は、ビニール袋を持って、手には軍手または、ビニールの手袋をつけて銀杏の採取に向かいます。銀杏が潰れたりするとにおいが強烈で、気を付けて採取をします。
採取した銀杏を処理するのも大変です。我が家では、昔からある方法として、ネットに入れて、地中に埋め、2~3週間寝かせておき実を腐らせて種だけになった状態で取り出し水洗いをするというやり方です。採取から下処理まで面倒ですがそれだけに味わって食べる銀杏の味は格別です。
最後に銀杏の美味しい食べ方、そして、銀杏を食べるにあたって注意すべき点をまとめてみたいと思います。
銀杏は、私が冒頭に紹介した食べ方の他に銀杏の炊き込みご飯や、副菜としての塩炒り銀杏、銀杏のてんぷらなど、かなりのレシピがあるようです。この中でも私はてんぷらが大好きなので一度我が家の奥様にお願いしようかなと思ったりもしています。
最後の最後になりますが、銀杏を食べるにあたっては、昔からも言われていることですが、
食べすぎには要注意ということです。いわゆる銀杏中毒と言われている中毒ですが、体調や栄養状態が悪く体内のビタミンB6が少ないと中毒になりやすくなるということなので十分注意して銀杏を美味しく食べるように気を付けましょう。

大相撲9月場所を振り返って!
大関貴景勝(27)=常盤山=が、千秋楽の逆転で4度目の優勝を果たした。本割で関脇大栄翔との4敗対決を制して優勝決定戦に進出し、11勝4敗で並んだ東前頭15枚目の熱海富士(21)を下した。2016年秋場所の豪栄道以来のかど番V、現役力士の優勝回数で単独2位に浮上した。
横綱照ノ富士が全休し、新大関豊昇龍とかど番の霧島が共に2桁勝利に届かない中で、意地を見せた。
「優勝以外、目指していない」と宣言して臨んだ7度目のかど番場所はいきなり初日に北勝富士に敗れ、中盤には2連敗もあったが突き押しを貫いて13日目には熱海富士に完勝し、単独トップから引きずり降ろした。14日目に豊昇龍との大関対決で敗れたが、気持ちを切らさなかった。
場所前から、自身に言い聞かせるように「負ければ弱くて(番付が)落ちるし、勝てば強い」と繰り返してきた貴景勝。4度目の賜杯を足掛かりに、番付の頂点を目指す。
以上が中日スポーツの今朝の記事であるが、今場所は、千秋楽にクライマックスがやってきたという感じがする。千秋楽までで単独トップで走っていた熱海富士が、我が郷土の朝乃山に敗れて、4敗になったことにより、その時点で、4敗勢にもチャンスが巡ってくるという展開に変わり、相撲ファンにとっては、この上ない最高の盛り上がりになったからである。
今場所は、序盤から期待されていた大関陣に負けが続き、先行きに暗雲が漂う厳しい状況になった。特に新大関の豊昇龍 が5日目までに3敗を喫し、霧島においても序盤で2敗を喫するなど場所の盛り上がりが心配されたが、それを救ったのは、前頭15枚目の熱海藤ではないかと思う。また、高安も9日目に勝ち越すなど、まだまだ、やれるんだという気概が感じられた。特に高安は何度も優勝決定戦に絡むなどあと一歩のところで賜杯に手が届かないという不運さが感じられるが、心配なのは体力の維持ではないかと思う。
いよいよ来場所は、貴景勝の連覇なるか、上位陣が奮起して場所を盛り上げるか楽しみな場所でもある。特に郷土力士の朝の山の活躍も期待したい。
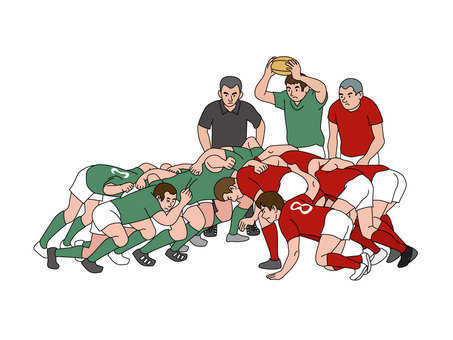
ラグビーワールドカップ対イングランド戦!
今日のイングランド戦を楽しみに朝早くから起きて、テレビの前に陣取って試合のゆくえを固唾をのんで見守っていましたが、残念ながら結果は34-12で敗戦となりました。試合を振り返ってみると前半4分、日本は自陣でのミスから相手にペナルティゴールを与え、先制を許しますが、前半15分に敵陣で相手の反則を誘うと、初戦のチリ戦で全てのキックを成功させた松田選手がペナルティゴールを沈め、同点に追いつきます。
さらに、前半23分にも松田選手が再びペナルティゴールを沈め逆転に成功。
ここまでは、イケイケでリズムよく戦ってはいましたが、その後、自陣でのラインアウトのミスからトライを決められ再逆転され、それでも、前半ペナルティゴールの奪い合いで、結局は前半4点差で折り返しをして後半戦に望みをつないだまではよかったのですが、いかんせん、日本に後半16分、相手の頭に当たったボールの処理で、相手にトライを奪われる結果となり、ここから試合のリズムが完全にイングランド側に傾いた気がする。私もてっきりノッコンだと思ったがテレビのリプレイを見て完全にノッコンではないと悟ったところです。ただ残念なのはその後のボールの処理ではないかと思う。イングランドは、この好機を逃さず、楽々トライ。このシーンは本当に日本にとっては不運、イングランドにはラッキーな結果となったのではないかと思ったところです。
ただ、試合内容全般を見る限り、日本もある程度イングランドに対して互角に戦っていたし、スクラムにおいても十分対抗できることも証明できたことは大きな収穫ではなかったかと思う。試合運びで長年の経験と実績を持つイングランドに最後は勝利の女神がほほ笑んだというところではないかと思う。
この経験を生かして、次のサモア戦には最善を尽くされんことをにわかファンとしての私は是非願うところです。頑張れニッポン!

即席ラーメン記念日!
今朝いつものように朝のラジオで、羽田美智子のいってらっしゃいの番組を聞いていたら今週の8月25日は、即席ラーメンの日だということを初めて知った。
この即席ラーメンの日のいわれは、昭和33年8月25日、日清食品から世界初の即席ラーメンである「チキンラーメン」が発売されたことに因んで制定されたことに由来するものだということであるが、このチキンラーメンの生みの親である創業者の安藤百福については、NHK朝ドラ「まんぷく」でその妻・仁子(まさこ)とともにその夫婦の半生をモデルに、懸命に生き抜いた夫婦の物語であったが、朝ドラファンとしては、このドラマを機に即席ラーメンができるまでの涙ぐましいまでの苦労を知って、即席ラーメンに対する価値観がガラッと変わったことをよく覚えている。
ところで、今改めて、この即席ラーメンを考案するにあたって、目標としたところは、5つの条件であり、
・おいしいこと
・簡単に調理できること
・長い間保存できること
・手ごろな価格であること
・衛生的で安全であること
以上の5つの条件が目標であったらしい。
今、ドラマ「まんぷく」のストーリーを思い出してみると、この即席ラーメンを考案するにあたって、安藤百福の目指すところは、戦後の食糧難の時代にラーメン屋の前で、長蛇の列に並んで、一杯のラーメンを待つ人々に対していかにおいしくて、安価な即席ラーメンを提供するかという上の5つの条件を満たすラーメンを作るためいろんな試行錯誤を繰り返して最後には、お湯をかけるだけで2分間待てば美味しい即席ラーメンが食べられるという結果にまでたどり着いたということは、大変な努力ではなかったかと思う。
現在即席めんはラーメンに限らず、その他の麺類までに広がっており、更にカップ麺も発明され、世界的にも保存食としての重要性も確認されている。
そう考えてみると安藤百福のこの即席ラーメンの発明は、偉大な人類への貢献といっても過言ではないような気がする。今この即席めんは更に進歩し続けており、この即席めんの影響を受けて他の食品においてもこのような即席で食べられる食品が増えていることは災害対策、或いはその他の利用価値を含めて今後期待するところは大きいと思われる。

023.7.24
豊昇龍優勝おめでとう!
関脇・豊昇龍(24)=立浪=が初優勝を果たした。3敗で並んでいた西前頭17枚目・伯桜鵬(宮城野)を本割で下し、優勝決定戦では3敗を守った西前頭9枚目・北勝富士(八角)を押し出しで破り賜杯を獲得した。
優勝を決めるといつもの険しい表情が一変した。引き上げた花道で涙をぬぐった。その理由を表彰式のインタビューで問われると、「泣いちゃったですね。すごくうれしくて我慢していたんですけど止まらなかったです」と振り返った。
優勝25回を誇る元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏の甥。レスリングの留学生として来日。他競技を学ぶために両国国技館で本場所を見て、力士への思いが強くなった。ダグワドルジ氏と相談して相撲への転向を決断。それだけに優勝の喜びを伝えたい人を問われ、「一番最初に親方に…。そのあとに叔父さんに伝えたいです」と話すと会場が爆笑に包まれた。
大関取りがかかった今場所は12勝で昇進目安の直近3場所33勝。取組後に昇進を預かる佐渡ケ嶽審判部長(元関脇・琴ノ若)が八角理事長(元横綱・北勝海)に(昇進を検討する)臨時理事会の招集を要請。この段階で事実上の大関昇進が決まった。
以上スポーツ報知の記事より。
今場所は、見どころが一杯の場所であったように思う。先ず第一に関脇3人による大関とりの場所であること、それに、横綱照ノ富士の連覇なるか、はたまた、落合改め、伯桜鵬が幕内でどれだけ通用するかこういったところが今場所の見どころであったように思うが、残念ながら、横綱照ノ富士については、3日目の翔猿戦で、翔猿のしつこい取り組みに敗れて腰を痛めてしまったのか翌日から休場を余儀なくされ連覇の夢を絶たれてしまった。通常の場所なら、落ち着いた相撲で退けるところ膝の故障など全身のけがが災いした結果となったように思う。次に伯桜鵬については、予想以上の好結果だったように思う、千秋楽まで優勝戦線に踏みとどまり、豊昇龍戦についても臆することなく豊昇龍をにらみつけるなどその強心臓には、将来の大器の予感さえしたほどである。
次に関脇3人の大関争いについては、序盤から中盤までは、ほとんど横一線で見ごたえのある内容であったが、大栄翔、若元春の二人については、終盤戦に崩れてしまったのが残念に思われる。来場所以降に期待したい。
その他では、新大関霧島はあと少しのところで、復活できなかったのが残念である。最後に地元富山県の朝乃山については、よく頑張ったと思う。7日目に対戦した豊昇龍戦で背中を痛めて、翌日から休場となったが、12日目に復帰して翔猿戦に勝利してから大関霧島、若元春に勝利して結果勝ち越しをしたのは来場所に向けての明るい材料になったと思われる。いよいよ来場所がまた楽しみである

2023.7.2
自動車運転 高齢者講習について!
先日自動車運転・高齢者講習を最寄りの自動車学校で受講することができました。内容については、以下の3項目について実施されたわけですが、人数の関係で、3組に分かれて、順番に受けることになりました。改めて、自動車を運転するについて自覚する内容が多々ありました。それについて、それぞれ、感想を述べたいと思います。
まず、私の組については、最初は、教習所内のコースを回りながら、スピードは指定された速度で運転しているかどうか、一旦停止は、きちんと所定の白線の手前で、止まっているかどうか、信号の見落としはないか、それと、高齢者に多い、段差に乗り上げたときに、慌てず、車を止めて、ゆっくりバックして、元のコースに戻れるかどうか等、いくつかのポイントで教官のチェックを受けることになりました。
私と言えば、信号のない交差点での一旦停止で、少し白線を超えてしまい。減点対象になった模様です。
次に行われたのは、目の検査で、これもいくつかポイントがありますが、視力検査はもとより、動体視力検査、夜間視力検査、視野測定検査などがありましたが、運転しながら周囲を見ることも必要だと感じました。これは、わき見運転ではなく、運転しながら、周囲に気を配るという運転で、危険予知運転とでも言いましょうか、そういう運転も必要なのかなと感じました。私の場合特に気を付ける必要があるのは、夜間視力検査で、改めて、夜間の運転はなるべく控えたほうが良いという結果だったように思います。高齢者は一般的に言って夜間運転は危険だという状況を確認したところです。
最後に受けたのは、30分程度の動画を見たわけですが、実際の事故事例を動画で見ることにより一層、車を運転するということに注意をすべきだと感じた講習ではありました。
お陰様で、高齢者講習は、無事に終わることができましたが、自分が高齢者であり、無理な運転は絶対にしないと強く誓ったところです。

2023.6.28
パフェの日の由来!
6月28日は何の日か分かりますか。私は、血糖値が高いので、なるべく甘いものは控えめにしていますが、この日は、パフェの日だそうです。全く、こじつけで、パフェの日としたようですが、その由来の意味がとても、面白いので、雑話に取り上げてみました。
以下その由来についての説明を紹介したいと思います。
実は、1950年(昭和25年)6月28日に、プロ野球の巨人軍藤本英雄投手が。日本プロ野球史上初の「完全試合(パーフェクトゲーム)」を達成したことに因むものだということです。
英語の「完全な(perfect)」はフランス語で、「パフェ(parfait)」
フランスでの「パフェ」は卵黄に砂糖や、ホイップクリームを混ぜて型に入れて凍らせたアイスクリーム状の冷菓に冷やした果物を添えて皿で供する冷菓。ということで、「パーフェクトゲームの日が転じて「パフェの日」となったようです。
ところで、この完全試合は、青森市営球場で巨人対西日本パイレーツとの試合だったそうです。ところが、この日、球場には取材記者は居たものの、カメラマンが一人もおらず、結局この記念すべき日の写真は全く残っていないそうです。
なお、この藤本投手は日本で初めて、スライダーを投球した投手と言われています。
以上が、パフェの日の由来の説明になりますが、藤本以来日本での完全試合達成者は16人この中には、平成での槇原投手、最近では、WBC代表選手の佐々木朗希がいますが、パフェの日の由来と野球との関係何となく関係なさそうで関係があるのが面白く雑話に取り上げてみました。
2023.5.29
照ノ富士復活優勝おめでとう!
14日目に8度目の優勝を決めた照ノ富士が、有終の美で締めくくった。貴景勝を土俵下まで吹っ飛ばす完勝劇。「2ケタ優勝という思いを強く持って過ごしていたので、それにちょっとでも近づくことができたのはうれしい」と、かみしめた。支度部屋での記念撮影で賜杯と幼い長男を抱くと、険しかった表情がようやく緩んだ。
両膝の手術と4場所連続休場を乗り越え、14勝の好成績で1年ぶりに賜杯を抱いた。「出るからには最後まで優勝を争うのが横綱としての宿命」との思いを結果につなげた。「とりあえず今場所は終わったので、来場所に向けてもう一回、体と向き合ってやっていきたい」と先を見やった。目標まではあと2つだ。以上報知新聞ニュースより
今場所は、横綱照ノ富士の復活優勝なるか、霧馬山の連続優勝なるか、好調関脇陣の巻き返し優勝なるか、話題の多い場所であったように思う。それを裏付けるように、横綱照ノ富士を中心として、見応えのある熱戦が連日行われたことは、相撲ファンとしても嬉しい場所であったように思う。
ことに、郷土富山県出身の朝乃山が場所終盤まで優勝争いに関わる熱戦を繰り広げたのは、とても嬉しいことであったと思う。ただ、12日目の関脇大栄翔戦、13日目の横綱照ノ富士戦を見た限りでは、まだ上位陣との力の差があるように感じた。来場所は予想番付では幕内の4枚目あたりまで復帰するような感じではある。この際しっかりと稽古をして、再び大関に復活することを期待したい。
そのほかでも、11枚目の北青鵬、16枚目の王鵬などは今後に期待できる関取ではないかと感じている。
いずれにしても来場所も3関脇の大関取りの場所として、横綱照ノ富士の連続優勝なるか見所の多い場所になるよう期待している。


2023.3.27
霧馬山優勝おめでとう!
大相撲春場所は、昨日3月26日千秋楽を終えて、新関脇霧馬山が優勝決定戦の末、小結大栄翔を突き落としで破り初優勝を飾った。本割を再現するような決め手で大栄翔を破ったのには多少驚きの念を隠せなかったが、本割と違うのは決定戦での物言いが入ったことではなかろうか。それだけ、この一番にかける両者の意気込みがあったのではないかと思う。
おそらく大栄翔としては、考えた挙句得意の押し相撲で行くしかなかったのではないかと思う。それに対して、霧馬山は、充分そのことを意識して対応した結果、優勝決定戦の一番になったのではないかと思う。いずれにしても両者の気合の入った良い相撲内容であったと思う。
その他の状況を見ると、翠富士の活躍も今場所の大きな見どころであったように思う。10日目までは、単独トップで、後続と2差があり、このままいくと優勝の可能性もあるのではないかと思えたぐらいに絶好調だったが、11日目に若元春、12日目に若隆景の兄弟に敗れてから、善戦むなしく、5連敗を喫してしまったのは、非常に残念な結果だったと思う。来場所は、是非この経験を生かしてほしいと思っている。
大栄翔については、残念な結果に終わったが、12勝3敗は、優勝同点であり、来場所は関脇として、大関にチャレンジする位置取りにあり、その後の結果次第では、大関とりのチャンスも巡ってくると思われる。精進をして来場所に備えてほしい。
最後にわが郷土の朝乃山残念ながら十両連続優勝とは成らなかったが、13勝2敗での成績は、今後に大きく自信をつけた内容ではなかったかと思う。来場所の幕内復帰はほぼ確実と思われて。是非、心技体充実した中で、幕内での活躍を期待したい。
2023.3.10
震災12年目に思うこと!
東日本大震災からはや12年が経ちますが、今でも地震発生当時のことはよく覚えています。というのも、当時その時間帯は、私は社労士として、中国の技能実習生の法的保護講習をやっていた最中だったからです。
発生した瞬間、通訳の女性の方が、電柱の線が揺れていますよ、地震じゃないですかという呼びかけに、私も、エツという感じで外の電柱、電線を見たら確かに揺れているのが確認できたので、実習生の皆さんにはとりあえず、安全のために外の駐車場に出てもらって、車のラジオの電源を入れたら、東北地方で、地震が発生したことを速報で流していたのを聞いて、東北で発生した、地震が何で、こんなに遠い富山県まで影響が出るのかと訝りつつもとんでもない巨大な地震が発生したのだと、帰宅して、夕方のテレビを見てようやく理解できたことを思い出します。
その後については、皆さんもご存じのように津波による大災害、福島原発のメルトダウン、悲劇的なニュースが、その後も連日続いて放映されていたことを思い出します。
あれから12年その間復興のために費やした、長い期間は、大変な期間だったといまさらながら感じる次第です。今なお、心に深い傷を負った方もおられます。そのことを考えると
長いようで、短い期間でもあります。
今、個人的に何ができるのかと考えたとき、この震災の出来事を私たちも家族を通して、忘れずに伝えること、次に、何よりも、分かっていることではありますが、生命の大切さを忘れずそのためにできることを日ごろから、身に着けていくことが大切だと改めて思うことです。折しもつい最近、トルコ・シリア大地震が発生し、5万人以上の方がなくなられています。決してよそ事でないことを改めて感じることが大切だと思っています。
2023.2.13
春の花、梅のこと!
立春も過ぎ、日々温かさを感じる今日この頃、毎朝聞くともなしに聞いている“羽田美智子のいってらっしゃい”。先週は、梅がテーマに上がっていましたが、今回はこの“梅”を題材に話をしてみたいと思います。
2月6日から10日までの5日間、梅についての話を聞かせてもらった訳ですが、いずれも印象深くどれを話題にするか、多少迷ったところですが、特に現在の元号とゆかりのある話や、桜と梅との対比の話など興味深く感じたので、月曜日の話題を中心に思いを話してみたいと思います。
現在の元号の「令和」の由来は、万葉集の序文に出てくる以下の内容
『初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、氣淑(きよ)く風和(かぜやわら)ぎ、梅は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひらき)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす』とあります。
この文言の意味は、
『初春の良き月、空気は清く澄みわたり、風はやわらかにそよいでいる。
そんな中、鏡の前の美しき女性の白粉(おしろい)のように、
梅の花が白く咲き、蘭の花は、御香のような香りをただよわせている』とあります。
そして、元号が令和に決まった背景については
厳しい寒さの後に、春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日本人が、明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたい・・・との願いが込められているとされています。
以上が月曜日に流れていた話ですが、最後に羽田美智子が感想として述べている、春の花というと桜に目が行ってしまうが、長い冬の後に最初に春を告げる花は梅であり、希望が持てる日本であって欲しいと願うところは私もまったく同感です。桜同様、梅についても春の花としての感慨を持ちたいと思うところです。
2023.1.23
大関貴景勝優勝おめでとう!
大相撲初場所千秋楽(22日、東京・両国国技館)、大関貴景勝(26=常盤山)が幕内琴勝峰(23=佐渡ヶ嶽)との相星決戦をすくい投げで制し、12勝3敗で13場所ぶり3度目の優勝を果たした。今場所の横綱昇進はならなかったものの、春場所(3月12日初日、大阪府立体育会館)で再チャレンジの権利を確保した。(以上ネットニュースより)
今場所10日目までは、9勝1敗と順調に勝ち星をあげていたが、11日目琴の若に敗れて2敗となり翌日霧馬山に敗れて連敗を喫し3敗目になると、ここで心が折れて、先の見通しが暗くなるところ、何とか踏ん張って持ちこたえたのが良い結果になったと思う。
貴景勝は確かに心も以前から見ると強くなっていると感じる。大関としての強い自覚がそうさせるのかもしれない。優勝を決めた一番でも琴勝峰をすくい投げで破っているがこの取り組みも心の中でイメージしていたように思う。以前ならば、がむしゃらに突っ張って前へ突進し土俵際でかわされるか、四つに組まれて負けるところ今場所はすくい投げで勝つ相撲が出てきたので相撲の幅が広がってきたように思う。
今場所はまた、大関候補として有力な若手がしのぎを削った場所でもあると思う。関脇の若隆景、豊昇龍、小結の霧馬山、琴ノ若、若元春いずれも力をつけてきている。
それと何よりもうれしいのは、わが郷土力士の朝乃山が14勝1敗で十両優勝を飾ったことがとにかく一番嬉しいことです。来場所は、編成会議の結果次第ではあるが、何とか幕尻でもよいから昇進できれば、今場所のように千秋楽結びの一番で大関貴景勝との優勝決定の一番が見れるかと思うと心がワクワクする感じがします。
相撲ファンとしては、来場所もよい取り組みを期待したいと思っています。
2023.1.5
七草粥について!
正月三ヶ日が過ぎると何だか胃が重いように感じてさっぱりした食事がしたいというような欲求に駆られるのは私ばかりではないと思うわけですが、そこで、今回の雑話は、七草粥について話をしてみたいと思います。
そもそも七草粥の由来は、1月7日の「人(じん)日(じつ)」の日に行われる「人日の節句」の行事で、江戸幕府が定めた五節句のひとつです。遡ればその起源は中国の前漢時代の新年の占い、唐の時代の七種菜羹という7種類の若菜を入れて無病息災を願うようになったことがその起源と言われています。
この風習が奈良時代に日本へ伝わると、年のはじめに若菜を摘んで食べ、生命力をいただく「若草摘み」という風習や、7種類の穀物でお粥を作る「七種粥」の風習などと結びつき、「七草粥」に変化していったとされています。
七草粥が定着した背景には、お正月のご馳走に疲れた胃腸をいたわり、青菜の不足しがちな冬場の栄養補給をする効用もあり、この日に七草粥を食べることで、新年の無病息災を願うようになったといわれています。
では、七草粥には何を入れたらよいのかというと、一般的には、以下のように春の七草と言われています。
1. 芹(せり)……水辺の山菜で香りがよく、食欲が増進。
2. 薺(なずな)……別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材でした。
3. 御形(ごぎょう)……別称は母子草で、草餅の元祖。風邪予防や解熱に効果がある。
4. 繁縷(はこべら)……目によいビタミンAが豊富で、腹痛の薬にもなった。
5. 仏の座(ほとけのざ)……別称はタビラコ。タンポポに似ていて、食物繊維が豊富。
6. 菘(すずな)……蕪(かぶ)のこと。ビタミンが豊富。
7. 蘿蔔(すずしろ)……大根(だいこん)のこと。消化を助け、風邪の予防にもなる。
以上が基本的には七草粥の材料になりますが、もともとの由来や、起源を考えるとこの春の七草に限らず、7種類の新鮮な野菜であれば、冷蔵庫にあるいろんな野菜を入れてもよいとされています。要は、正月のごちそうで疲れた胃腸をいたわる具材であれば、何でもよいということになります。
2022.12.19
今年の漢字から受ける感想!
毎年年末に日本漢字能力検定協会がその年の世相を表す漢字一 字とその理由を全国から募集し、最も応募数の多かった漢字を今年の漢字として発表していますが、今年の漢字として選ばれたのは「戦」で、10,804 票 (4.83%)を集めて、2001 年以来 2 度目の第 1 位となりました。そこで、今回の雑話は、この「戦」が選ばれた理由をいくつか紹介するとともに、2位、3位までの候補の漢字及びその理由を紹介するとともに、私の感想を述べてみたいと思います。
まず今年の漢字として「戦」を選んだ理由は
・ウクライナへロシアが侵攻し戦争へ。コロナ感染症との戦い、温暖化対策対立の戦い、サッカーワールド カップでの戦いなど、国内外とも戦いの連続である。 (東京都/83 歳)
・やっぱりロシアの軍事侵攻という戦い、今年も続いているコロナとの戦い。そして、ロシアの蛮行による 石油や小麦などの価格高騰による物価高との戦い。戦いに明け暮れている今年を象徴して「戦」を選び ました。 (滋賀県/67 歳)
・冬季オリンピックで「戦」って最多のメダル数取得、将棋の藤井聡太棋士が苦「戦」の結果、初の 10 代で の五冠。ウクライナとロシアの「戦」争、参議院選挙の激「戦」、旧統一教会問題で悪「戦」苦闘続きの国会。 (静岡県/44 歳)
次に2位の漢字の「安」を選んだ理由
・今年は大きく二つの出来事がありました。一つは、参議院選挙の投票日直前に起こってしまった安倍元 総理への銃撃事件。民主主義国家であってはならない事件が起こり、人々は不安に。もう一つは、ロシア 軍によるウクライナ侵攻。原料価格も高騰し、不安が高まった。北朝鮮による度重なるミサイル発射に、J アラートが鳴る回数も増え、安全保障の議論も活発化。 (山口県/55 歳)
3位「安」を選んだ理由
・コロナ禍もまだまだ続いていますが、今年はようやく行動制限が緩和されて、旅行や各地でのイベント も開催されてきていて、ようやく楽しい事が増えてきたように思えます。とにかく今まで我慢してきた ので、行動制限緩和で心から楽しめる事が増えました。楽しみが増えると笑顔も増える、今年はこれで 決まり。 (栃木県/36 歳)
以上今年の漢字についてその理由を見てみると、ロシアのウクライナ侵攻、それによる経済への影響、いろんな意味で、戦争による影響が取りざたされた1年ではなかろうかと思うところです。
また、依然として続くコロナとの戦いについては、どうすれば共存できるのかに舵が切られてきているように思います。それと、今年最高の明るい話題はサッカーの日本代表の活躍ではなかったかと思います。森保監督のもと、日本代表が、ドイツやスペインに勝った試合は、感動的でした。そういう意味で来年は平和で明るい年であるように祈りたいと思います。
2022.11.28
阿炎関優勝おめでとう!
大相撲福岡場所で平幕の阿炎が12勝3敗で並んだ大関・貴景勝と平幕・高安との三つ巴の優勝決定戦を制して初優勝した。単独首位だった高安を本割で撃破し、決定戦で連勝した。3場所連続平幕優勝は優勝制度が導入された1909年夏場所以降で初。阿炎は20年7月場所中に新型コロナウイルス対策のガイドライン違反で3場所出場停止処分を受けたが、常に支えてくれた入院中の師匠・錣山親方(元関脇・寺尾)や家族らに恩返しを果たした。
以上スポニチ報道の内容であるが、昨日は、この取組をテレビで見ていて、本当に感動的な内容であったように思う。本来なら本割で高安が勝っていれば高安にとっては、悲願の初優勝になるところであったが、勝負の世界は確かに厳しい。
大関時代から優勝にあと一歩というところまで近づいていた機会が何度もあったが、高安の性格か或いは勝負運に見放されているのか、ここ一番のところでいつも優勝の女神から見放されているのが現状である。優勝決定戦では、阿炎との一番で、思わぬ敗戦、脳しんとうを起こしたのかしばらく立ち上がることが出来なかった。残念な結果だが、次の場所以降に奮起する以外にないと思う。
一方阿炎については、悲願の初優勝、この間新型コロナウイルス感染対策に反する会食を行ったため、3場所の出場停止処分を受け引退届まで提出したが、家族と別居して部屋に住み込むことなどを条件に慰留された。猛省した阿炎は幕下から出直し、改めて相撲道にまい進することを決意。結果として今回の初優勝につながっている。
今回の福岡場所はいろんな意味で戦国時代の様相も帯びている。大関正代の負け越し陥落、関脇御嶽海の大関復活ならずの負け越し。来場所からは一横綱一大関の場所がやってくる。関脇若隆景、豊昇龍も力をつけてきている。
又富山県的には朝乃山の来場所での十両復帰が確実になっており、来場所以降の大相撲の取組に期待したい。
2022.11.20
富山弁 “きのどくな”から感じる暖かい感じ!
先日、元文化放送アナウンサーの吉田照美の放送の中でこの“きのどくな”という言葉を久しぶりに聞いた。この言葉久しぶりに聞いたわけであるがその瞬間何となく懐かしいという思いと同時に、暖かい感じがした。
そのわけは何だろうか、思うに小さい頃に、近所のおばあちゃん達がよく使っていたことを思い出したから だろうか。この“きのどくな”という言葉、富山弁で端的にいえば相手に対する感謝の言葉なのであるが、私なりに子供のころに感じていた感情は、相手に対して気使ってくれてありがとうというような感じで年寄りの方々が社交辞令を交えて使っていたような気がする。
今思い出しても、その頃の風景とともにこの言葉を懐かしく思うと同時に月日の経つのは早いものだと感じたところです。
2022.8.22
虫の声 秋
朝10分程度、健康のため散歩をするのが日課になっていますが、お盆が過ぎてここ最近感じるのは、虫の声が賑やかになっていることです。あまりそういうことに無頓着なはずなのに何故か早朝の静かな雰囲気の中で耳に入ってくるのがこの虫の声。
この虫の声を聞くといよいよ夏が終わり、秋のシーズンになってくるのかなと思うことです。そういえば、空を見ると夏の雲ではなく秋の雲が段々と多くなっているような気もします。
いろんな情景の中で、夏から秋へと衣替えが進んでいるような気がします。
あれ、松虫が鳴いている。
ちんちろちんちろ、ちんちろりん
あれ、鈴虫も鳴きだした。
りんりんりんりん、りいんりん。
秋の夜長を鳴き通す、
ああ、おもしろい虫のこえ。
これは童謡“虫のこえ”の一節ですが、小学生のころに音楽の授業でよく歌った童謡です。何となく懐かしさを感じるとともにその抒情感に深く感じるところがあります。
2022.8.9
「長崎の鐘」のこと!
こよなく晴れた 青空を
悲しと思う せつなさよ
うねりの波の 人の世に
はかなく生きる 野の花よ
なぐさめ はげまし 長崎の
ああ 長崎の鐘が鳴る
これは「長崎の鐘」の一番目の歌詞であるが、子供のころによく聞いた歌でもある。当時はこの歌の深い意味、或いは感慨を考えたことはなかったが、この歌の持つ深い意味を知ったのは、朝ドラのエールを見てからである。
「長崎の鐘」とは、廃墟となった浦上天主堂の煉瓦の中から、壊れずに掘り出された鐘のことであるが、この鐘が掘り起こされたいきさつ、それから再び、鐘が鳴り響いた時の喜び、希望を朝ドラエールの第95話の中で感動的に見たことを記憶している。
思うに、この「長崎の鐘」が世に出るまでのいろんな変遷を見るにつけても平和であることの大切さをあらためて感じる思いがする。
今日はまさに77年目の長崎原爆の日でもある。この「長崎の鐘」に込められた平和への思いをあらためて心に刻みたい。
2022.7.25
逸ノ城初優勝おめでとう!
大相撲名古屋千秋楽。平幕逸ノ城が、12勝3敗で初優勝を遂げました。先に宇良との対戦に勝利していた逸ノ城が横綱照ノ富士との相星決戦を待っていた支度部屋で、横綱照ノ富士が、大関貴景勝に敗れたことにより、初優勝が決定したものです。
これまで、13勝、14勝挙げても達成できなかった優勝に手が届いたことで、初土俵から8年かけてようやく念願の初優勝を遂げたことにお祝いを述べたいと思います。考えてみれば、初場所から初関脇に至るまで、わずか5場所での昇進は、当時、このまま横綱まで、行ってしまうのではないかと当時そんな感想で相撲を見ていました。
ところが、その後腰痛や右肩のけがの影響で休場するなどしておととしの初場所では十両にまで番付を落としました。先場所はコロナの感染により、休場し、今場所は、休場明けの場所でした。そんな場所での初優勝は言葉数の少ない逸ノ城にも感慨ひとしおではなかったかと思います。今場所は、コロナウイルス感染症が急拡大した影響で、休場する関取も多く相撲協会も来場所の番付決定では苦労されるのではないかと思われるところです。
ところで、私の今場所の楽しみは、郷土出身力士の朝乃山の取組だったわけですが、うれしいことに7戦全勝で3段目優勝を果たし、来場所はおそらく幕下まで上がってくると思われますが、しっかり精進して、照ノ富士が果たしたように、大関復帰、そしてできれば横綱を目指して頑張ってほしいと願うところです。
2022.7.10
貝原益軒養生訓より!
今回は、貝原益軒の養生訓について話をしてみたいと思います。貝原益軒は、当時としては、長寿の85歳まで生きられた方だけに、養生訓の内容も具体性を帯びた有益な内容が多いかと思います。
自分としては、養生訓を全て読んだわけではなく、詳細な内容はわかりませんが、全体に通じる、養生の基本的な考え方は、自分の体と心を大切にする内容ではないかと思っています。幾つかの項目について順にみていき自分なりの考えを述べていきたいと思います。
養生の道
- 怒りや心配事を減らして心を穏やかに保つ
心のバランスを保つ上では、怒りや、心配事を完全になくすことは不可能だけど、
少しでも前向きな心を持つことは大切だと思っています。
- 元気であることが生きる活力になるのでいつも元気でいる
いつも笑って、元気な態度でいることは相手に対しても元気を分け与えることが出来
結構なことだと思います。
- 食事は食べ過ぎず、毎日、自分に合った適度な運動をするのがよい
確かに食べ過ぎたと思うとき、食後の不快感があり、腹八分の心構えでいきたいと思い
ます。加えて、朝早く10分程度の散歩も習慣づけをしたいと持っています。
- 生活の中で自分の決まり事をつくり、よくないことは避ける
自分なりに小さなことでもよいから決まり事をつくり、それに従った日々の行動に気を
つけることは良い事だと思います。しかも自分なりによくないと思ったことはなるべく避け
たいと思っています。
- 病気になってから治療するのではなく、病気にならない努力をする
この言葉非常に同感します。私も70歳代になると、未病対策がいかに必要かと思
い、何となく体の不調を感じたら、医者に相談したいと常日頃から感じています。
- お金がある、ないに関係なく、自分なりの楽しみを持って生活する
私は、お金は全くありません。けれども、それなりに毎日楽しく過ごせているのは、自分
なりに小さな楽しみを持っているからではないかと思っています。
以上幾つかについて、自分なりの感想も含めて話をしてみましたが、確かにその他の面においても細かい養生の内容が記載されていて参考になります。
一度じっくりと養生訓全編について目を通してみたいと思っています。
2022.6.8
紫陽花の話!
梅雨のこの時期、見ごろなのは紫陽花の花ではないでしょうか。今回はこの紫陽花について話をしてみたいと思います。
紫陽花は大きく分けて3種類に分けられますが、一般的にはホンアジサイを指すことが多いようです。私も紫陽花というとホンアジサイをイメージします。
紫陽花の花について誤解しやすいのは一般的に花びらだと思っている部分は「ガク」と呼ばれる葉っぱが変形したもので、実際の花は「ガク」の内側に小さく見えるのが本当の花ビラだそうです。
マア、そのことは置いといて、何といっても梅雨のこの時期、雨露に濡れた紫陽花は何といっても美しく心を癒してくれるような気がします。
私の住む隣町の護国寺は通称シャクナゲ寺とも言われていますが、シャクナゲの季節が終わると、ツツジや紫陽花等も美しく咲きます。眼下に日本海を眺められる絶景の下で紫陽花をめでるのも楽しいかとも思います。
私の家の田んぼの納屋の隣にも例年紫陽花がきれいに咲き誇ります。確かに梅雨の時期に咲く紫陽花は晴天の下に見る紫陽花とは一味違って、美しく見えます。
やはり紫陽花は露に濡れた紫陽花が最高に見栄えがあるような気がします。
2022.5.23
横綱照ノ富士優勝おめでとう!
大相撲夏場所は、昨日千秋楽を迎え、横綱照ノ富士が大関御嶽海を寄り切りで破り7度目の優勝を飾った。この一番、頭をつけての万全の相撲でこの一番にかける執念を感じた相撲であったように思う。
今場所は、横綱照ノ富士が前半で3敗を喫する取り組みの中で千秋楽まで持つのかどうか心配されたが、徐々に取組に工夫を凝らして、下がらない取組に徹したのがその後の取組内容を改善するきっかけになったのではないかと思う。
それだけ日々一番一番大事に取り組みに全力を尽くした結果が優勝という最高の結果を呼び込んだのではないかと思う。
それにしても残念なのは大関陣の結果ではなかろうか、勝ち越したのは、大関貴景勝のみで結果も8勝7敗と大関として褒められる結果ではなかったのではなかろうか。大関正代、大関御嶽海の2大関は負け越し、大関正代に至っては、ここ数場所大関らしからぬ取り組みが続いている。
これに対して、今場所は、三賞に輝いた、大栄翔、隆の勝、佐田の海は、しっかりと結果を残し、夏場所を盛り上げた功績は大きいと思う。特に大栄翔は初日に横綱照ノ富士を一方的な押し出しで破るなど、地力が確実についている状況が伺われ、今後が楽しみである。
いよいよ、来場所からは、我が郷土出身の朝乃山が6場所の停止処分が明けて出場する。この期間どのように準備してきたのか楽しみな場所でもある。
是非来場所も相撲ファンが楽しめるような場所であることを期待したい。
2022.4.18
大仏についての雑話!
今回は、大仏についての話をしたいと思います。毎朝、ラジオから流れる羽田美智子のいってらっしゃいを何気なく聞いているわけですが、先週の話題は大仏についての話がテーマになっていました。
この大仏さんの話となると、私は、今でも中学生時代の修学旅行のことが思い出されます。それは、私の年代の前までは、京都・奈良が定番であったあった修学旅行が、私らの学年と1年後輩の学年については、関東が修学旅行の行き先に変更になりました。その変更理由は、東京オリンピック開催の理由によるものでした。今から思えば、私の中学2年の10月10日に東京オリンピックが開催され、日本中が沸き上がっていたことを思い出します。その理由から関東地方へ行き先が変更になったわけです。
それまでの関西への修学旅行の目的地の一つに奈良の大仏さんがあり、私らの関東地方への目的地の一つには鎌倉の大仏さんがありました。
いずれも、大仏さんが目的地の一つになっており、何となく因縁めいたものを感じています。
奈良の大仏は、聖武天皇の願いで奈良時代の752年、東大寺の仏殿につくられました。高さは約15mあります。
当時、政治的な争いや、水不足からくる飢饉、地震、さらに天然痘の大流行など、たいへん苦しい時代でした。そこで聖武天皇は「仏教の力によって、すべての人々が心安らかに暮らせる世の中になるように」という思いから建立されたそうです。
一方奈良・東大寺の大仏と並んで、古くから知られているのが鎌倉の大仏です。神奈川県鎌倉市・高徳院のご本尊「阿弥陀如来坐像」のことで、高さは約11.3mあります。
しかし鎌倉の大仏には、わからないことがたくさんあるそうです。一説には、東大寺の大仏をお参りして感動した鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝が、「鎌倉にも大仏をつくろう」と計画したものだと言われています。
そんな“いわれ”があろうとは、当時は思いもよらないこと、単純に大仏の大きさに感心するのと、同級生との修学旅行の楽しさを満喫するのに一杯だったことをいまさらながらに思い起こしたりもします。
今、大河ドラマで鎌倉幕府のことがテーマになっていますが、何となくそのことにつけても当時を懐かしくも思ったりもします。
2022.3.28
若隆景関優勝おめでとう!
大相撲春場所千秋楽は27日、千秋楽を迎え新関脇の若隆景が高安関との優勝決定戦で、上手出し投げにより破り、初優勝を飾った。新関脇の優勝は、双葉山以来86年ぶり、福島出身の力 士としては、栃東以来3人目50年ぶりの快挙となった。
今場所は、横綱照ノ富士の途中休場により、俄然面白くなってきた。その中で新大関の御嶽海の連覇も見えてくる場所ではあったが、終盤に至り、元大関高安、新関脇若隆景、琴ノ若の3人も加わり、千秋楽まで目の離せない取り組みが続くこととなり、相撲ファンとしては、毎日の取組内容が楽しみな状況になったように思う。
その中で、高安が、一歩前へ出ているような感じがして、最終的には高安優勝かと思ったが、そこは勝負の世界、11日目に若隆景に敗れて、連勝が10で止まり、先行きに陰りが見えてきたように思う。その後はやはり元大関、御嶽海、高景勝の大関を破り、いよいよ、優勝が見えてきたかと思われたが、14日目、千秋楽で大関正代、関脇阿炎に連敗し、一気に優勝戦線が波乱に満ちた状況になった。考えてみれば、優勝を意識し過ぎた結果が、勝敗に影響してきたのではないかと思われた。結局その中で、新関脇若隆景は、千秋楽まで高安ほどには、緊張感がなかったのが幸いしたのではないかとも思うところです。
とにかく今場所は意外な面がいろいろあって楽しませてもらえたと思います。その中でも大関正代については、6日目までに1勝5敗、いよいよ、負け越し大関陥落かと思われたが、何かのきっかけで相撲内容がガラッと変わるものだと思いました。7日目からは、6連勝で最終的には。優勝戦線にも影響を与え、14日目高安、千秋楽若隆景も破り、9勝6敗となり、カド番脱出。大関としての面目躍如といったところだったと思います。
いよいよ、来場所が5月に開幕しますが、今場所同様相撲ファンを楽しませるような取り組みを期待したいと思います。
2022.3.9
11年目を迎えた東日本大震災に思うこと!
今年も3月11日がやってくる。昨年は10年目の区切りということで、各メディアは、特番を組んでの放送が多かったが、今年は今時点ではそれほど目立った特番は無いようである。
今思うことは、当時の未曽有の災害を決して忘れてはならないということではないかと思う。今でも震災発生当時のことを憶えている。
当日は、技能実習生の講習のため富山にいたが、発生当時の瞬間を生生と記憶している。中国人の通訳さんのこれは地震ではないですかという言葉に実習生全員に外の駐車場に出るように伝え、車のラジオをつけて、東北地方に大きな地震があったということを知ったわけであるが、東北地方で発生した地震が富山にまで伝わるのはよほど大きな地震だったということを後になってようやくわかった次第である。
今でも、特に福島県の原発の被害にあった地域の人はいまだに放射能汚染の除染が終わっていないこともあって、自宅に帰れない人も多いと聞いている。震災の爪痕は、その他の地域でも同様であり、元の自宅に戻ることをあきらめた人も大勢いると聞いている。
そうこう考えてみると、11年がたったからということで復興した外形だけで判断するのは早計だと思う。当時の状況その後の状況をしっかりと見届け後世に伝えていくことがこれからできることではないかと思うところです。
2022.2.4
今日は立春。この日に思うこと!
2月4日今日は立春。季節の上では、今日から春ということですが、まだまだ肌寒く春という感じは受けませんが、それでも梅の花が咲き始め徐々に暖かくなるなり、春の初めとなります。
なるほど、確かに雪は降って積もりますが、溶けるのも早くそれだけ地面の温度も上がっているのかもしれません。立春の声を聴くと何となく長い冬が終わりいよいよ春が来るという気持ちの高揚感もあります。
昨日は、節分。最近は節分で豆まきという感じではなく恵方巻がすっかり定着し我が家においても恵方巻を頂きました。今年の方角は北北西ということで、気持ち北北西に向かって恵方巻をいただきました。
最近恵方巻で食べ残しが問題になっているようで、我が家においても食べれる分量の恵方巻を当日買い求めていただきました。この日に食べる恵方巻はこの日に食べることに意味があるように思えて、その意味ではとても美味しく感じました。
また今日から北京で冬季オリンピックが開催されます。オミクロン株の急拡大で北京でも大変な厳戒態勢の中で行われるオリンピックということで、参加選手もpcr検査を頻繁に受けなければ大会に参加できないということで苦労も多いかと思いますが、しっかりこの4年間の成果を発揮してほしいと思います。期待のスピードスケートや、フィギュアスケート等楽しみな競技が沢山あります。テレビでしっかり応援したいと思っています。
2022.1.24
御嶽海優勝おめでとう!
大相撲初場所は、1月23日千秋楽を迎え、12勝2敗の関脇御嶽海と11勝3敗の横綱照ノ富士の対戦となり、関脇御嶽海が横綱照ノ富士を寄り切りに破り3度目の優勝を飾った。これにより、大関昇進も確実となり、両手に花の最高の結果となった。
今場所は、大関貴景勝がけがのため早々と途中休場するなど波乱の場所となったが、前頭6枚目の阿炎や、14枚目の琴ノ若の活躍で、あわや優勝決定戦は巴戦かと思われたが、結局は本割で御嶽海が照ノ富士を寄り切りに破って勝負は決した。この千秋楽の一番、今までの照ノ富士なら難なくこらえて、挽回していたはずだが、場所中に痛めたかかとのけがのため踏ん張りがきかず、こらえることができず、寄り切りに敗れたというのが実態ではなかろうかと思われる。
それにしても今場所は、それなりに大相撲の将来という点では、いくつかの明るい兆しも見えてきたのではないかと思われる。阿炎や琴ノ若は勿論のこと、大栄翔は負け越したとはいえ、後半戦は連勝で結果は7勝8敗まで盛り返したこと。阿武咲、豊昇龍もそれなりの結果を残したことは、相撲ファンの私にとっては、楽しみなところではある。来場所も熱戦を期待したい。
2021.12.23
冬至にカボチャを食べてゆず湯に入るのは何故!
昨日は冬至。今回の雑話は表題のとおり、冬至にカボチャを食べてゆず湯に入るのは何故ということで話をしてみたいと思います。
ゆず湯に入るのはゆずの強い香りが邪気を払い、皮に含まれている油の成分が皮膚の乾燥を防いで体を温めることで1年間風邪を引かないといわれているからだそうです。又、冬至にカボチャを食べる理由は、カボチャは保存食として他の野菜に比べ格好の野菜であったこと、栄養も豊富でビタミンAのもとになるカロテンを多く含み、免疫力アップが期待できるということで、昔からカボチャを食べると風邪を引かないといわれていることがその理由に挙げられます。加えて、冬至は1年で夜が最も長く昼が最も短く、この日より、運が上昇することで縁起物としての野菜であることも冬至にカボチャを食べる理由だそうです。
なるほど、カボチャはまたの名をナンキン、英語で言ってもパンプキン。いずれにしても“ん”が2回もついており、運が上昇する野菜としては格好の野菜だと思う訳です。
昨日私は仕事を終えてからスーパー銭湯でゆずたっぷりのゆず湯につかり、夕食は、カボチャの温かい煮物をつまみに冬至の夜を楽しみながら過ごさせていただきました。正に感謝!感謝!の夜でした。
お問合せ・ご相談
担当:特定社会保険労務士 上田 建
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
※ただし、日中は外出も多いのでお急ぎの方は、下記携帯まで。
折り返し連絡を差し上げます。
富山県で社会保険労務士をお探しなら、下新川郡入善町の社労士・上田社会保険労務士事務所へどうぞ。
就業規則の作成・変更・見直しから、人事・労務管理のご相談、育児休業制度や介護休暇制度の構築、助成金の申請など、サポートいたします。
近隣の富山市、滑川市、魚津市、黒部市、朝日町にもお伺いいたします。ショッピングセンターコスモ21の近くです。駐車場もありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

